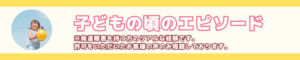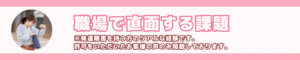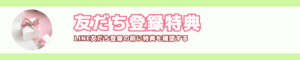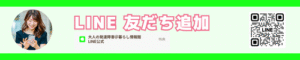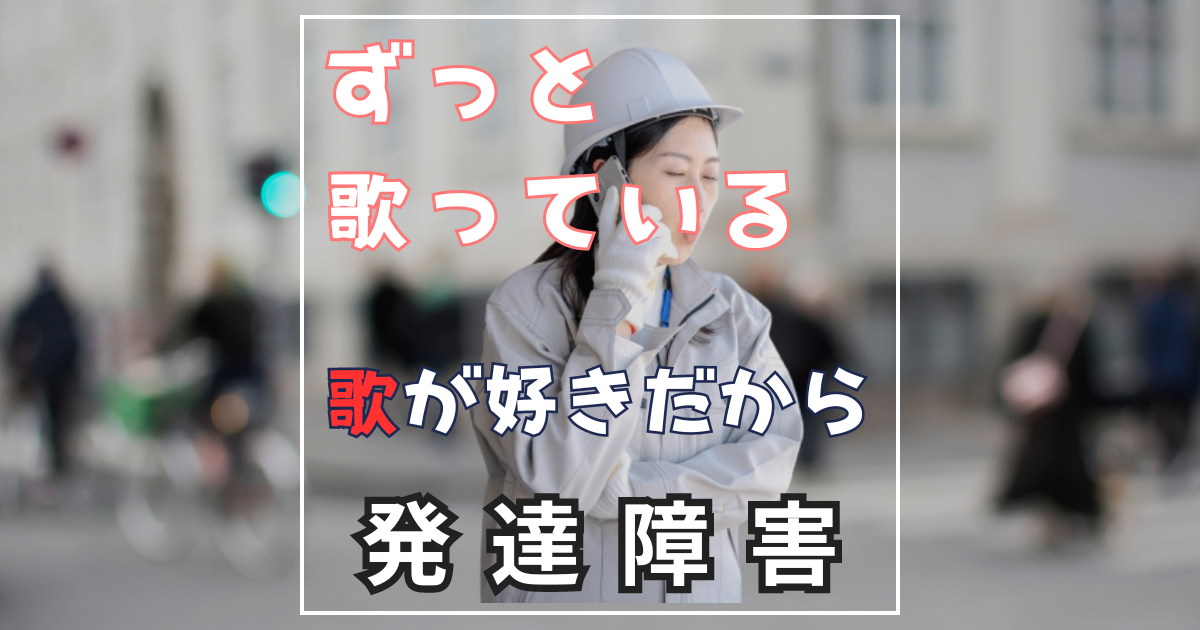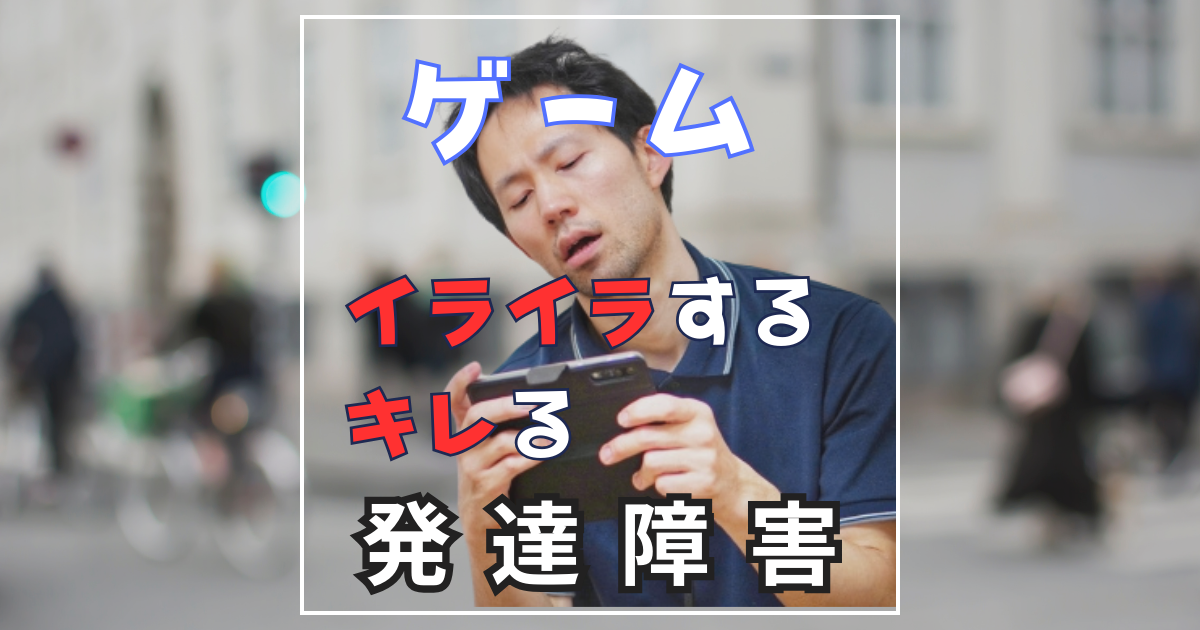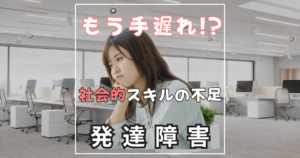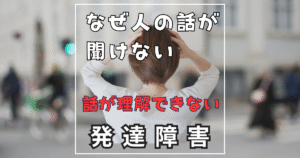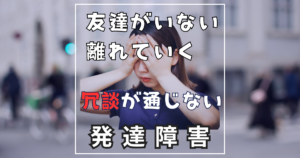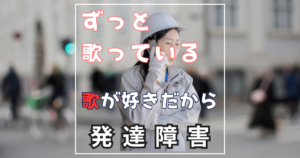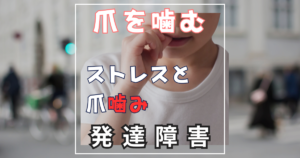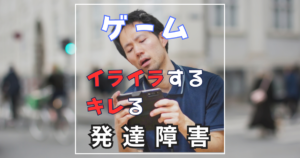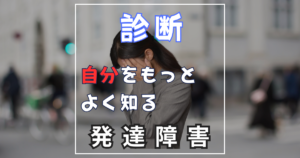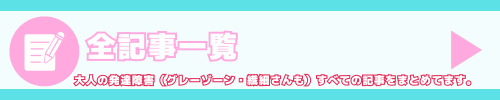
日常生活や仕事の中で、自分がなぜ周りの人と同じようにできないのか悩んだことはありませんか?
これまで何度も「努力が足りない」「もっと頑張らなければ」と自分を責めてきたかもしれません。
しかし、それが発達障害による特性の一部である可能性もあります。大人になってから発達障害に気づくことは珍しくなく、自分の特性を知ることで、適切な対策を取ることができるようになります。
この記事では、なぜ「大人の発達障害を自覚させる」・「大人の発達障害を自覚する」ことが重要なのか、その理由と具体的な影響について、まとめています。

大人の発達障害 【大人の発達障害を自覚する】
発達障害を持つ方が、自身の状態を自覚していない場合、周囲の人々にさまざまな影響を与えてしまうことがあります。
周囲を困らせてしまったり、迷惑をかけてしまったり…。
また、自分自身も発達障害であるという自覚がないことで、”発達障害ではない人々”と自分自身を比べてネガティブな気持ちになってしまうこともあります。

大人の発達障害であると自覚がない場合、「なんて自分はダメなんだ…」・「周りに理解されない」などの気持ちを抱いてしまうこともあります。
大人の発達障害を持つ方が、自分自身の障害について理解し受け入れることはとても大事です。
自分が発達障害であると自覚することで、必要な治療やサポートを受け、普段の生活で直面するいろいろな問題にうまく対応できるようになるからです。
そのためにも、本人が発達障害に気付いていない場合には、周囲が自覚するようフォローしてあげることも大切かもしれません。



「大人の発達障害である」と、自覚し理解することは人生において大きなポイントです。やっとスタートラインに立てると言っても大げさではありません。
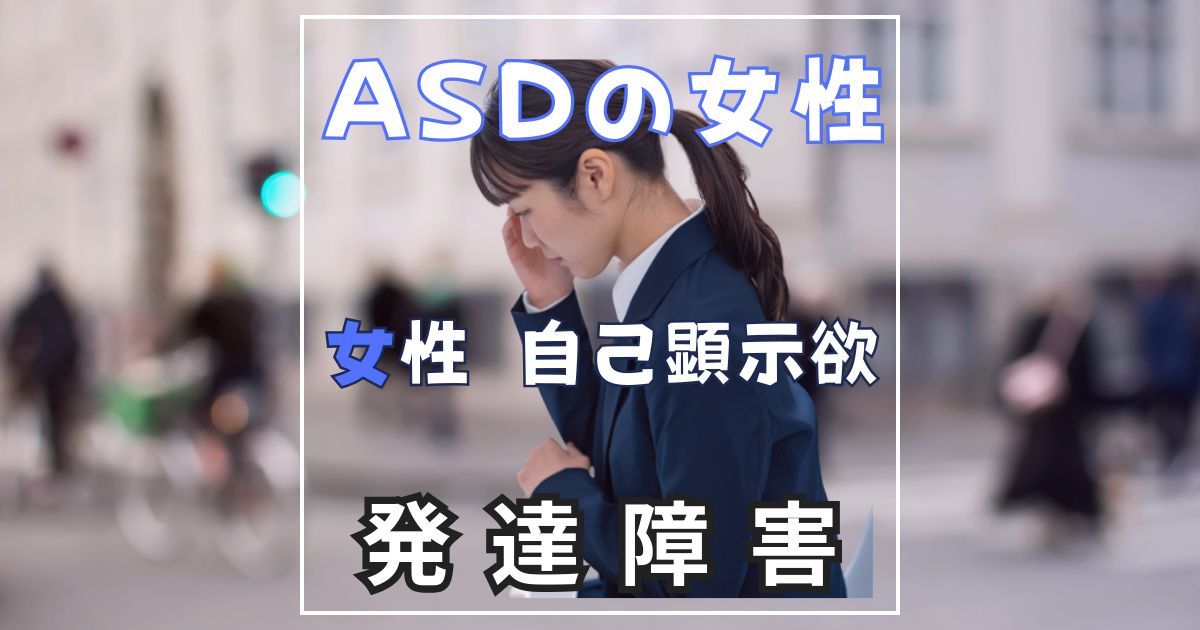
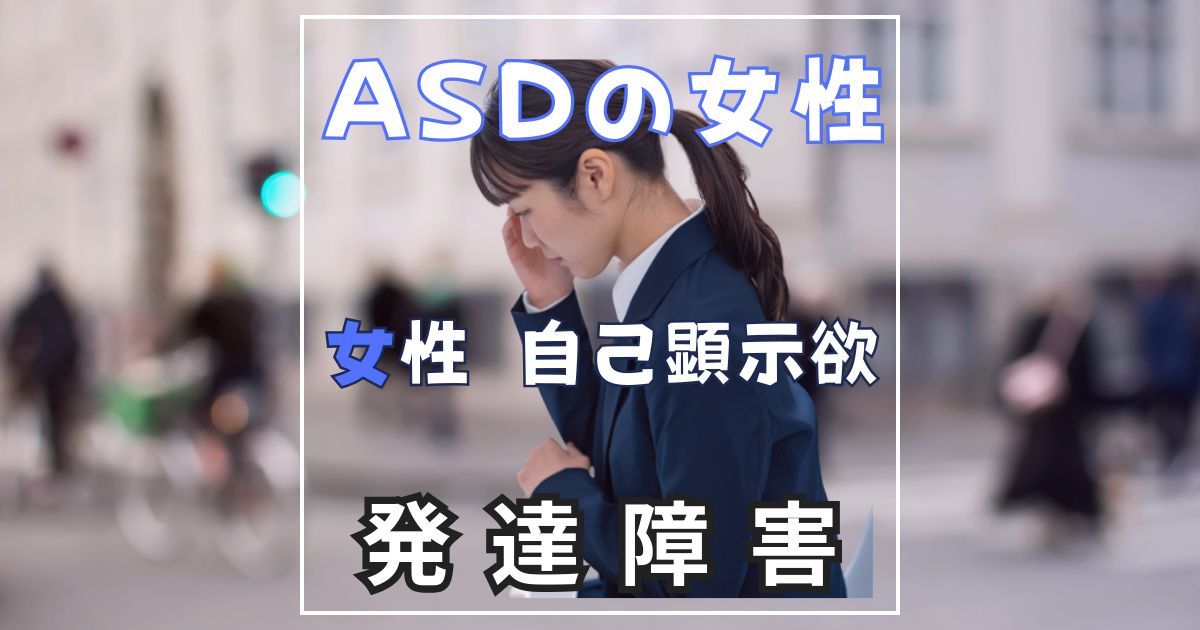
大人の発達障害 【大人の発達障害を自覚させるには】
ここでは、発達障害を自覚させるためのアプローチ方法を紹介します。
大人の発達障害を自覚させる【情報の提供と理解】
発達障害についての正しい情報を提供することで、本人が自分の行動や特性に気付くきっかけを作りましょう。
書籍、ネットや雑誌の記事、専門家のセミナーなどの情報源から、具体的な事例を交えて説明すると、わかりやすいです。
また、特性を理解し受け入れる態度を示すことも重要です。
そうすることで、本人が自己受容を深める手助けとなります。
大人の発達障害を自覚させる【指摘】
日常生活や職場での具体的な困りごとを優しく指摘し、それが発達障害の特性に関連している可能性があることを説明します。
たとえば、「忘れ物が多い」・「指示に従うのが難しい」などの行動が見られる場合、それがどのように発達障害の症状と関連しているのかを話し合いましょう。
大人の発達障害を自覚させる【専門家の受診】
本人が発達障害であることを受け入れ、自覚を持つようになったら、発達障害の専門家(医療機関やカウンセリングなど)の受診を勧めることも効果的です。
専門家による評価と診断によって自己認識を促進し、より適切な治療やサポートを受けられるようになります。
診断後のサポートや治療の選択肢についても説明し、一人で対処する必要はないことをしっかり伝えましょう。
大人の発達障害を自覚させる【サポート】
発達障害を自覚した後も、定期的に話し合いの時間を持ち、本人が抱える感情や困難に耳を傾けるなど、サポートを継続しましょう。
この過程は自分自身の特性について考えたり、理解を深める機会になります。



発達障害を自覚し、受容することは簡単ではありません。
しかし、周囲の適切なサポートと理解あるアプローチによって、発達障害である自分自身を受け入れる手助けができます。
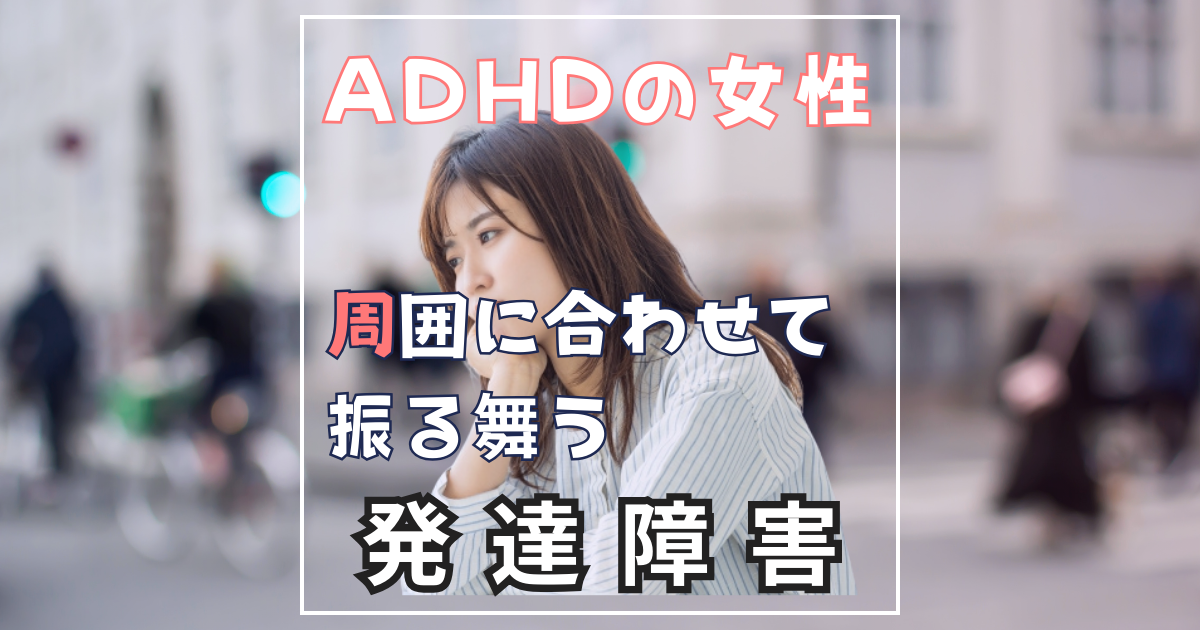
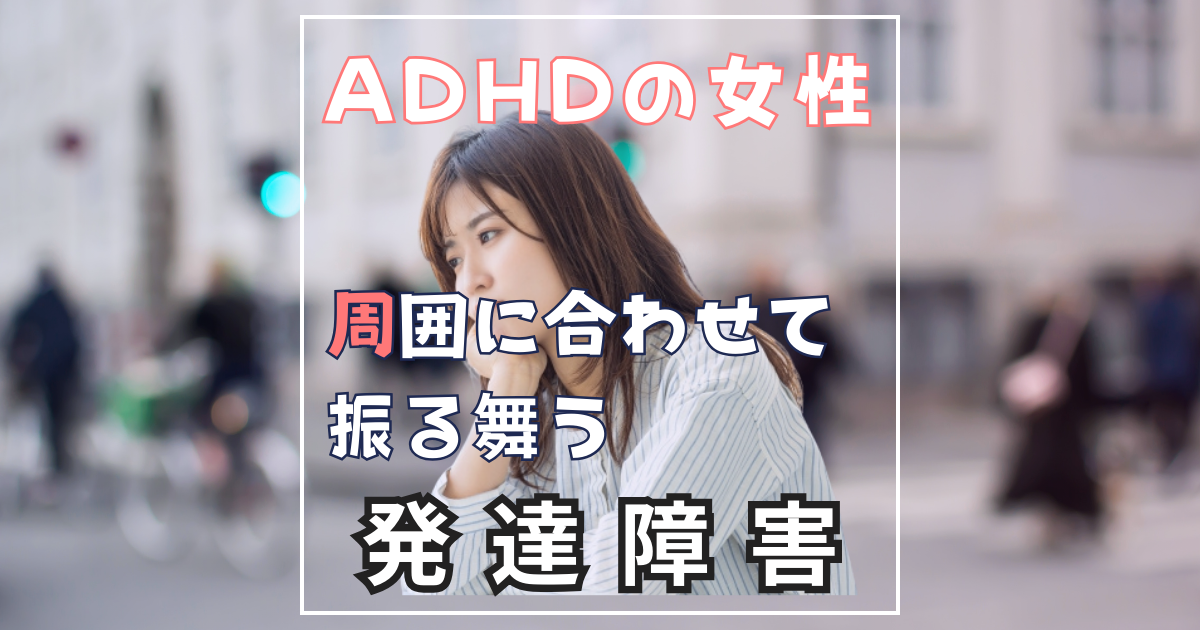
大人の発達障害 【大人の発達障害を自覚する】
大人の発達障害を自覚する【自己認識】
発達障害を持つ大人が、自分自身のことをちゃんと理解すること、これを「自己認識」と呼びます。
もっと簡単に言うと、「自分が何が得意で何が苦手かを知ること」です。
この「自分のことをよく知る」というのが、さまざまな困難に対処する手助けになります。
これを深く掘り下げて説明してみましょう。



「己を知る」という意味のことわざや熟語、格言は多く存在します。
発達障害を持っている、持っていないに関わらず「己を知る」ということは大切なことです。
まず、自分の得意なことや苦手なことを知ることは、仕事や日常生活で直面する問題をうまく解決するための第一歩です。
たとえば、ある人が地図を読むのがとても苦手だとします。
もしその人が「地図が読めない」と自覚していれば、迷子になりそうなときにはあらかじめGPSやスマートフォンの地図アプリを用意したり、人に道を聞いたりするなどの対策を講じることができます。
このようにして、事前に準備をすることで、困った状況をうまく乗り越えることができるわけです。
しかし、自分の苦手なこと、つまりここでは「地図が読めない」という弱点を理解していなかった場合はどうでしょうか?
迷子になってから、どうしよう??と悩み始めるのです。
事前に準備(迷子になる想定)をしておらず、その場で思いついた方法で乗り越えようとするので、ベストな解決方法ではない場合もあります。



迷子になって初めて、スマートフォンの地図アプリを起動しても、バッテリーが残り少なかったりと、急な対応ではなかなかベストな解決は難しいものです。


大人の発達障害を自覚する【自己認識が高まる】
次に、「自己認識」が高まると、自分で問題を解決する力がつきます。
これを「自己効力感」と呼びます。
自己効力感とは、「自分にはこれができる」と強く信じることができる力のことを指します。
たとえば、もし自分が数字に弱いと自覚しているなら、計算が必要な作業の際には事前に計算機を用意する、計算に必要な時間を多めに取るなどの工夫をします。
こうすることで、仕事中のミスを減らし、自信を持って取り組むことができるようになるのです。
自己認識が高まることによって、自分の強みを活かしたり、苦手なことをカバーする戦略を立てることができるようになります。
そして、仕事だけでなく、プライベートの生活でも充実感を感じることが増え、全体的な生活の質が向上するのです。
以上のように、「自己認識」を理解して高めることは、発達障害を持つ大人が直面するさまざまな課題に対して、より良い行動や方法で対処するために非常に大切なのです。
自分自身をよく理解し、その上で適切な対策を講じることで、生活全般の質を向上させることが可能になります。


大人の発達障害 【大人の発達障害を自覚すること】をより深くみていきましょう
ここからは「大人の発達障害を自覚すること」をより深掘りしていきましょう。
自覚していないとどうなる?
発達障害を持つ方は特にコミュニケーションに苦労することがあります。
たとえば、話の流れをつかみにくかったり、相手の感情や表情の意味を読み取るのが難しいのです。
これにより、他人と話しているときに間違ったタイミングで話を挟んでしまったり、場にそぐわないコメントをしてしまうことがあります。
例を挙げると、会議中に同僚が重要な発表をしている最中に、突然関係ない話題で話を始めてしまうことがあります。
このような行動は周囲の人々に理解されにくく、”空気が読めない”、”コミュニケーションが取れない”などと思われて職場や私生活での人間関係にひびが入る原因となります。



自分自身では相手を不快にさせているつもりがないのに誤解されがちなシーンが多いです。
自分を知ることの重要性
「自分を知る」とは、自分自身の特性や行動の傾向を把握し、それをうまく活かす方法を学ぶことを指します。
特に発達障害を持つ人が「自分を知る」ことは、自分の行動パターンを見つけ出し、人とうまくやっていく方法や、ストレスをうまく扱うコツを身につける助けになります。
自分がどんなことに敏感で、どんな時に強く反応してしまうかを把握しておけば、困った状況になる前に対策を考えることができます。
また、自分のことをよくわかっていると、自信を持って行動でき、職場でも自分の能力を十分に発揮できるようになります。



先ほども触れた「自己認識」、「己を知る」ということですね。
なんとなく、”自分はこういう性格”というレベルでの理解ではなく、1~100まで細かく自分という人間を説明できると理想的です。
自分を知るにはどうしたらいいのか
発達障害のある人が、自分自身を理解するためには、まず専門家によるカウンセリングを受けたり、適切な診断を受けることが重要です。
友人や家族、職場の同僚との日常的な対話やコミュニケーション、周囲からの指摘などがきっかけで、自分が発達障害かもしれないと気づくことがあります。
たとえば、職場の同僚からしばしば「話の流れが追いづらい」と指摘される、家族から「約束を忘れがち」と言われることが多い、などこれらの繰り返しの指摘により、自分自身に何らかの特性があるのではないかと考えるようになり、発達障害の可能性について更に専門家の意見を求めることに繋がるなどのパターンもあります。
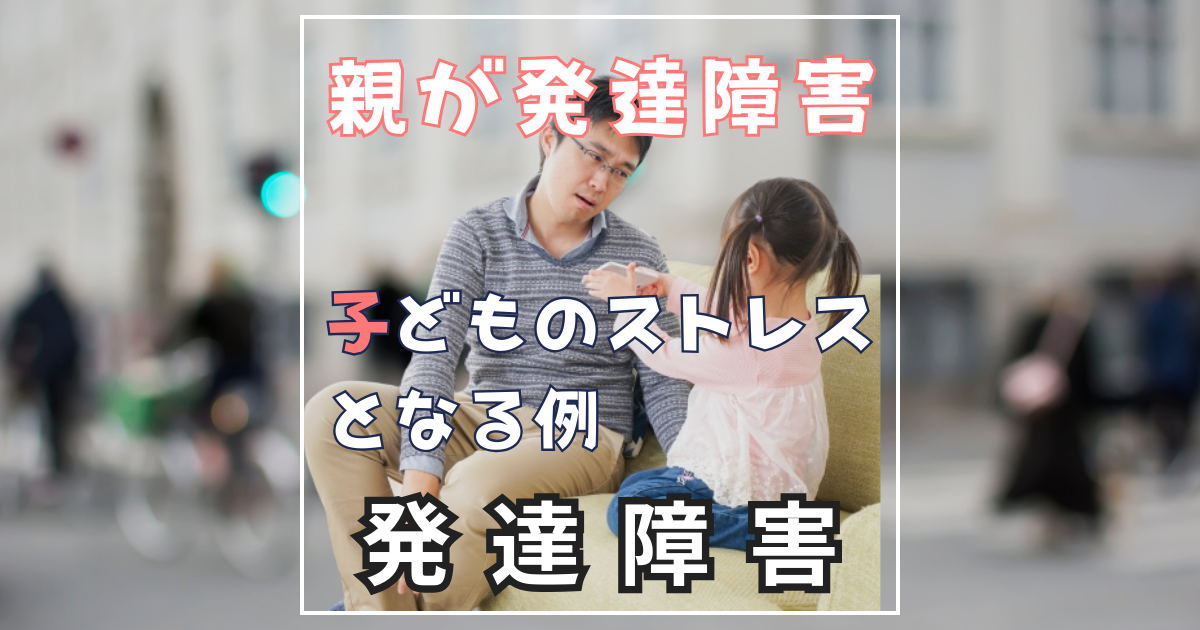
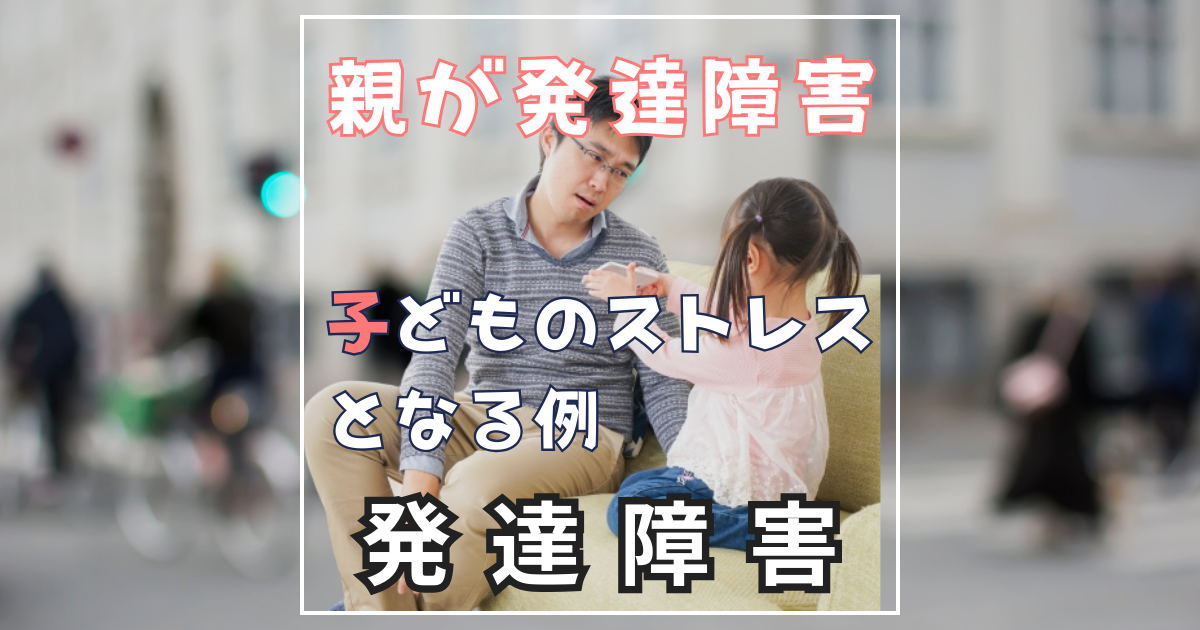
本記事に記載されている特徴は、発達障害を持つ全ての個人に当てはまるわけではなく、個人差があることをご留意ください。
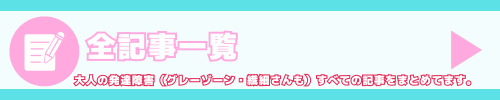
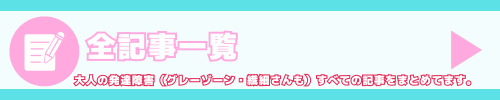


大人の発達障害@暮らし情報館とは



大人の発達障害@暮らし情報館について
大人の発達障害やグレーゾーンの方、またはご家族・職場の方・ご友人・パートナーに向けて、日常生活や仕事、人間関係をより安心して過ごすための工夫やヒントをわかりやすく紹介します。
家族や友人との関わり方、職場での伝え方、暮らしを整える方法など、社会生活全般に役立つ情報をお届けします。
本サイトの内容は、誤解を招きにくい表現に配慮しながら実践に移しやすい形に整理しています。
※本サイトは医療・法律・労務の専門的助言を提供するものではありません。個別の判断が必要な場合は、専門機関へご相談ください。



ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こちらの記事が少しでもお役に立てれば幸いです。