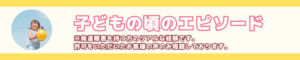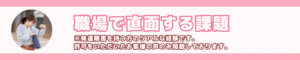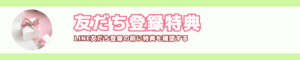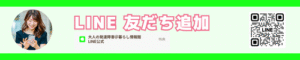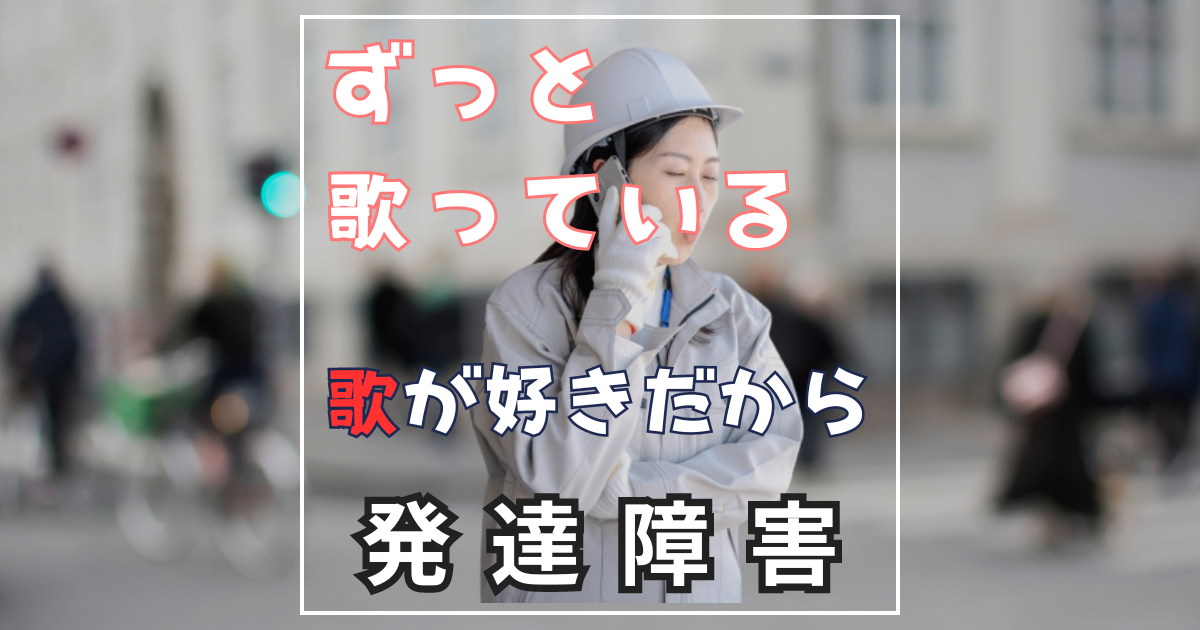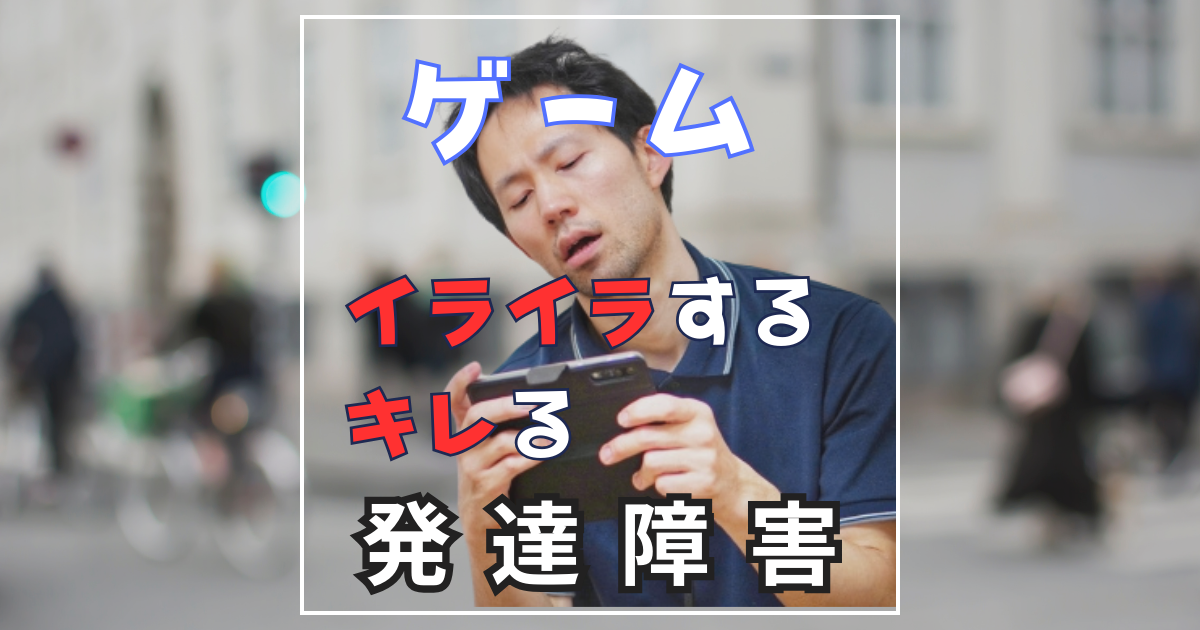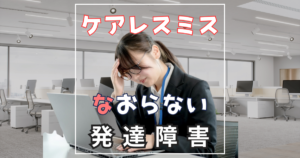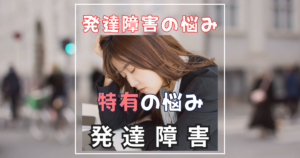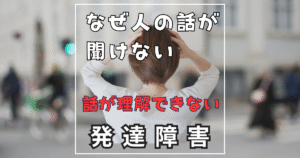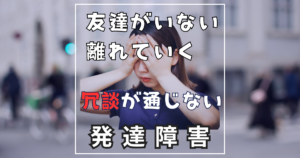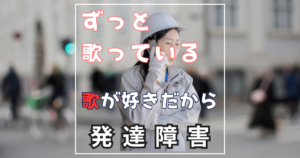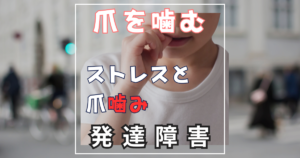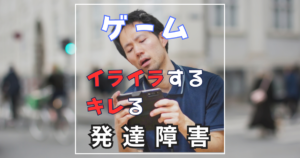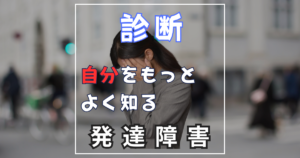近年、「大人の発達障害」という言葉を耳にする機会が増え、実際に社会に出てからその特性に悩む人も少なくありません。なかでも「仕事が続かない」「転職を繰り返してしまう」という悩みは、特に深刻です。一方で、適性や環境さえ整えば、自分らしく働ける可能性も大いにあります。
本記事では、大人の発達障害転職という観点から、仕事が続かない背景や具体的な対策方法について解説します。今の仕事に悩み、自分に合った働き方を模索している方や、周囲にそうした悩みを持つ方がいる場合にも役立つ情報をまとめました。
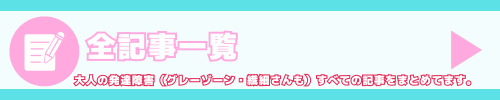

なぜ転職を繰り返すのか?~大人の発達障害ならではの背景~
仕事が合わないと感じる理由
1. 業務内容とのミスマッチ
大人の発達障害を持つ方の中には、注意力散漫や衝動的な行動などの特性があり、細かい事務作業や長時間の単純作業が苦手な人もいます。こうした特性に合わない職種に就くと、ミスを重ねるうちに自信を失い、結果的に辞めてしまうケースが多いです。
2. 職場環境との不一致
自分とは違うペースやコミュニケーションのスタイルを持つ職場だと、なかなか馴染めないことがあります。とくに※対人関係の微妙な空気感を読み取りにくい特性がある場合、同僚との距離感がつかめず、人間関係がうまく構築できないことが転職の引き金になることもあります。
※対人関係の微妙な空気感の例
・同僚が忙しそうにしているとき、話しかけてもいいのか迷う
・上司が遠回しに言っていることの本当の意図が分からない
・雑談の輪に入るタイミングがつかめない
飽きやすさ・衝動性による転職
1. 興味が移ろいやすい
ADHD(注意欠陥・多動性障害)などの特性を持つ人は、最初は意欲的に取り組んでも、新鮮味が薄れると急激にモチベーションが下がることがあります。一つの職場で同じような業務を続けるうちに、「もっと別のことをやってみたい」と衝動的に辞めてしまう場合があります。
2. 環境変化への適応が難しい
新しい仕事を始めても、周囲のサポートや理解が十分でないと、急な変化に対応できずストレスを強く感じてしまいます。その結果、辞めたい気持ちが強まり、また別の職場を探すという悪循環に陥ることもあるのです。
具体例~職場に馴染めず辞めてしまうケース
| 事例 | 原因となりやすい特性 | 結果 |
|---|---|---|
| 同僚の指示を真に受ける | 相手の冗談や皮肉に気づけず、言葉通りに受け取ってしまう | 誤解や衝突が重なり、人間関係がギクシャクして退職へ |
| 興味の移り変わりが激しい | 新しい業務には積極的だが、飽きると集中できなくなる | 生産性の低下で評価が下がり、モチベーションも急降下 |
| 細かいミスが続く | 注意力不足でデータ入力などの単純作業が苦手 | ミスの多さを指摘され、自信を失い転職を検討 |
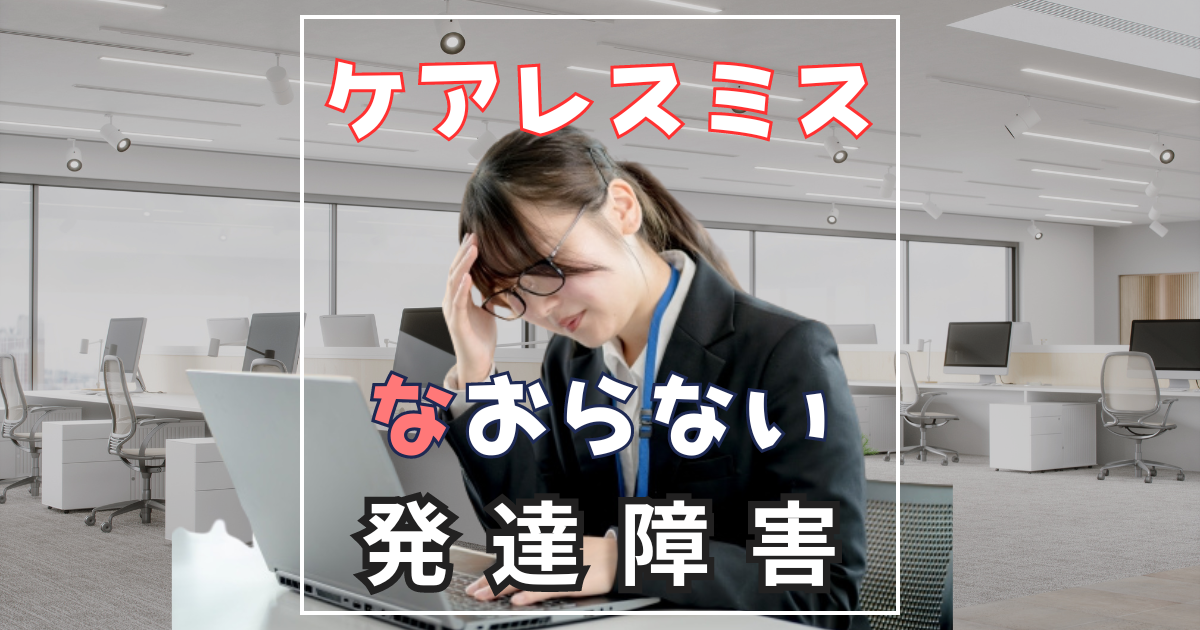
転職を繰り返す人の本音~どうして仕事が続かないのか~
周囲の期待に応えられないプレッシャー
新しい職場に入るたび、「今度こそ頑張ろう」と意気込む方は多いです。しかし、思うような結果が出ず、同僚や上司からの期待に応えられないと感じると、自己否定感が強まってしまいます。そのプレッシャーの重さから、転職を選択してしまうこともしばしばです。
理解のある環境を求めて
大人の発達障害の特性が受け入れられる職場を探すために、転職を繰り返すケースもあります。実際、発達障害への理解や配慮が足りない環境では、自分の特性を隠すか無理に合わせるしかなく、精神的な負担が大きくなるでしょう。「自分らしく働ける職場」を探し続けるうちに、転職回数が増えてしまうのです。
大人の発達障害転職~仕事を続けるための対策とポイント~
1. 自分の特性を理解しよう
- 得意分野と苦手分野をはっきりさせる
事務処理、クリエイティブ系か、人と接する仕事か(営業、接客)、一人で集中する仕事か、など、自分がどんな作業に向いているのかを客観的に整理します。 - 発達障害の診断やカウンセリング
必要に応じて医療機関やカウンセラーを活用し、具体的なアドバイスを得ることで、苦手な部分の対処法が見えてくることがあります。
2. 職場選び~業務内容と環境を重視
- 応募前に情報収集を徹底する
企業の雰囲気や業務内容を事前に調べ、特性に合わなさそうな業務が多い場合は検討し直すのも一手です。 - 就職・転職支援サービスを活用
発達障害者向けの就労移行支援や転職エージェントなどを利用すると、業務内容や職場環境の情報を詳しく教えてもらえる場合があります。
3. 職場での具体的対策
- コミュニケーションの工夫
冗談や皮肉が伝わりにくい特性がある場合は、相手の意図を確認したり、自分の理解度をこまめにフィードバックするなどして、誤解を減らすよう努めましょう。 - タスク管理の仕組みづくり
ミスや抜け漏れが起きやすい場合、デジタルツール(カレンダーアプリやタスク管理ソフト)を使って、やるべきことを可視化するのがおすすめです。 - 休憩やリセットタイムの確保
集中が途切れがちな方や飽きやすい方は、定期的に短い休憩を挟み、脳をリフレッシュさせることでミスを減らしやすくなります。

転職後の定着を助けるサポート体制
1. 社内支援制度の活用
最近では大手企業を中心に、メンター制度やカウンセリング窓口を設けている職場が増えてきました。自分の特性をオープンにしたうえで、どんなサポートが受けられるかを確認し、必要に応じて相談することが大切です。
2. 専門家や外部機関との連携
- 就労移行支援事業所
発達障害の方を対象に、職場定着をサポートするプログラムを用意している事業所があります。就労後も相談に乗ってくれる場合が多く、長期にわたる職場定着につながります。 - キャリアカウンセリング
自分の強みや適性を客観的に把握するために、キャリアカウンセラーに相談する方法も有効です。
成功事例~自分に合った職場で活躍できる可能性
以下の表では、大人の発達障害を持つ方が実際に転職を成功させ、自身の特性を活かして活躍している例を紹介します(あくまで一例です)。
| 事例 | 特性・強み | 職場での工夫 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Aさん(30代男性) | こだわりが強く、一つの分野を深堀りする力 | 自分だけのスペースを確保し、集中できる環境を設定 | 専門性の高い研究職で高評価を得て定着 |
| Bさん(20代女性) | コミュニケーションは苦手だがアイデア豊富 | 発言が苦手なので、チャットツールでアイデア共有 | 企画部で新しい発想が認められ、昇進も果たす |
| Cさん(40代男性) | 数字やデータ分析が得意で、細かいチェックが好き | 管理部門の書類作業をシステムで可視化して管理 | ミスが激減し、チームの業務効率アップに貢献 |
転職を繰り返す悪循環から抜け出すには
大人の発達障害転職と聞くと、「また仕事を辞めるのか」とネガティブに捉えがちです。しかし、正しい情報収集と自分に合った対策を講じることで、自分らしく働ける職場に巡り合うチャンスは充分にあります。
- 自分の特性や強み、苦手分野を把握する
- 職場選びの際に業務内容や環境をよく調べる
- 職場内外のサポート(メンター、就労移行支援、カウンセラーなど)を積極的に活用
こうしたステップを踏むことで、転職を繰り返す悪循環を断ち切り、長く働き続けられる可能性は大いに高まります。
焦らずじっくりと、自分に合う場所を見つけることが大切です。
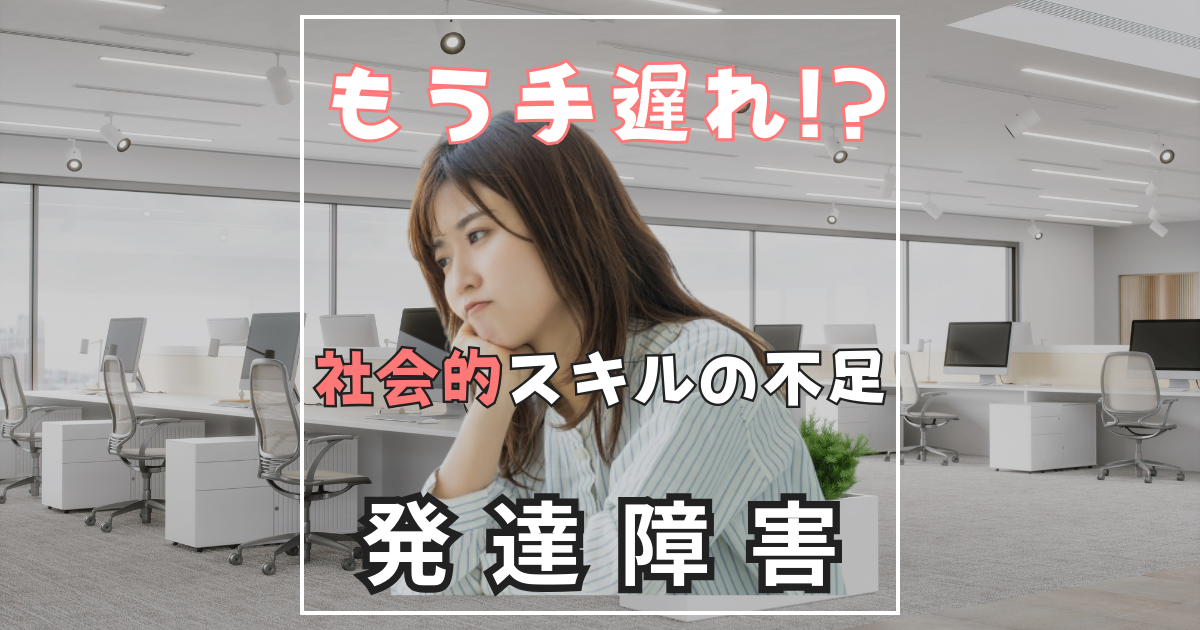
発達障害を持つ方が転職を繰り返すのは正しいのか? 専門家に聞いてみた
転職が多いと不利になる? 企業の評価とキャリアへの影響

発達障害を持つ方のサポートをお手伝いしております、鈴木祐貴”です。



転職のプロ”プロエージェント”です。



本日は発達障害の人が転職を繰り返すことは正しいのか?ということについて議論していきたいと思います。



よろしくお願いします。



よろしくお願いします。



早速ですが合わない職場や環境、心理的ストレスを抱えながら働くことは正解なのでしょうか?
それとも転職をしてリセットする方がよいのでしょうか?



日本の転職市場の性質も含めてお話をしたいと思います。



そうですね、さまざまな理由があるかと思いますが、結論、転職を闇雲に繰り返すことは転職のプロの目線から見てもあまりおすすめしません。



これは、発達障害の人に関わらずですが、よっぽど優秀な人、つまりヘッドハンディングなどのオファーがある人以外は転職回数には制限があると考えた方がよいですね。



でも、転職は何回してもOKですよね?



はい!日本の法律でも転職は”●●回まで”という縛りはありませんからね。



では、制限があるというのは・・・?



ルール上は何回転職してもよいですが、一定数以上の回数になると、転職自体が困難になります。



外資系や一部の日系企業を除き、日本は未だにキャリアアップのために転職を繰り返す文化が根付いていません。



なるほど。転職回数が多いと、転職活動で不利になるということですね。



はい。採用する企業は、転職回数が多い=すぐ辞める人・忍耐がない人・協調性がない人、と判断する傾向があります。



それなら、発達障害のある人が転職を繰り返すことが望ましくないということについて同意できます。



履歴書に多くの転職歴があると、雇用のハードルが上がることは否めません。



企業は投資対象としての従業員を求めており、教育や研修にかかるコストを考えると、短期間で去ってしまう可能性が高い人を雇用することを躊躇しますよね。



確かに、転職を繰り返すことは雇用者から見た場合、その人の安定性や長期的なプランに疑問を持たせる可能性がありますね。



また、採用は採用担当者や人事部の評価にも関わってきます。
採用後にすぐにやめると採用に係る広告費やリソースが無駄になってしまいますからね。



採用担当者の立場で考えると分かりやすいですね。



同じような経歴やキャリアの人が採用選考に進んだ時、転職回数や前職の在籍歴が考慮されます。



採用担当者としては、自らの評価を下げる可能性があるような選択はしたくないですよね。



つまり、転職回数が多いと”しっかりした企業”に入社するハードルが上がってしまうということですね。



はい。”しっかりした企業”の定義にもよりますが、そのような企業は採用を慎重に行いますし入社後のフォローやサポートも充実している場合が多いです。



反対に無条件で受け入れてくれる企業は、すべてがそうだとは言いませんが、環境に難があり離職率が高い傾向にあります。



いわゆる、ブラック企業ですか?



はい。とりあえず誰でもいいから採用したいという企業ですね。



入社のハードルが低いということは、あまりよくないということですか?



一概には言えませんが、”誰でもいいから採用”というスタンスの企業は、入れ替わりが激しいですからね。



入れ替えが激しいということは、上司や同僚も変わりますし、労働環境も安定せず、過酷な環境だったりします。



なるほど。それは発達障害を持つ人にとって、強いストレスを感じる環境ですね。



転職して新しい環境に適応すること自体が大きなストレスなのに、人が入れ替わる度、また新しく関係を築くのは大変なことです。



ここで大切なのは、転職を考える前に現在の職場でどのように成長できるか、また、どのようにサポートを得られるかを真剣に考えることです。



発達障害を持つ方の場合、特に職場でのサポート体制が、自分の成長や生活の質に大きな影響を及ぼしますからね。



はい。適切なサポートや理解があれば、転職を繰り返さずに済む可能性も高まります。



ちなみに発達障害を持つ方にはどのようなサポートが適切であると考えてますか?



例えば、仕事の管理方法やコミュニケーションのスキル向上のためのトレーニング、職場での理解と仕事の調整などが挙げられます。



また、外部の専門家や発達障害の特性を理解している方からのアドバイスも有効ですね。
大人の発達障害と言っても、個々により特性が異なるので具体的なアドバイスや努力の方法を示してもらえるのは心強いことです。



実際に多くの企業では多様性と包括性を重視しており、発達障害を含めたさまざまな特性を持つ従業員が活躍できるような環境作りに力を入れています。



そして、外部の専門家や発達障害を持つ方が頼れる存在がいれば職を変えるのとは別のアプローチも期待できますね。



はい。転職によってリセットを図る必要がなく、発達障害の人でも自分らしく働くキャリアを形成できると思ってます!



もし、職場にフォローしてもらえるような環境がなければ、自ら外部のサポートを探す、受けるという手段もあります。



外部のサポートとは、医者やカウンセラー、発達障害の方の理解者などですね。



はい。そうです。家族や身内、社内の人には相談し難いことでも、外の人にならありのままを話せるということも珍しくありませんからね。



ビジネスにおいても、外部のコンサルや、外注といった社外のネットワークは当たり前にありますからね。



社内に環境がないなら、自ら環境を用意すればいいという考え方です。



カウンセラーや外部のサポートは期間限定でもスポットでもいいと思います。
けど、いつでも相談できる先があるということがメンタルの安定にもつながります。



たしかにそうですね。ビジネスにおいても最初は外注で対応していた仕事も、経験を積み内製化することも珍しいことではありません。



発達障害の人が自分らしく働くために、嫌なことがあったり壁にぶつかった時に転職という手段を安易に選ばず、他の方法も模索してもらえると嬉しいです。



万が一、転職を検討する際には、そのような企業文化があるかどうかを見極め、自分が長く働ける環境を選ぶことが大切です。
これは、発達障害を持つ方に限らず、転職全般に言えることですけどね。



逃げるようにネガティブな意味で転職をするのではなく、今いる環境でどのようにすれば自分らしくいれるか考える方が建設的ですよね。



はい。結局、逃げるように転職すると、問題に向き合う力がつかずに逃げてしまう癖がついてしまいます。



例えば、転職した当初は環境や人に恵まれていても、後から苦手な人が
転職してきたり異動してくることもありますよね。



たしかにそうですね。せっかく自分らしく働いていたのに、苦手な上司が転職してきたことによって、がらりと環境が変わってしまうということはあり得ますよね。



問題を解決する力がないと、”自分が転職する”という方法しか取れないです。



そうなるときりがないですよね。ずっと転職をし続けなければいけないです。



30代、40代、50代と年齢を重ねれば重ねるほど転職のハードルは上がります。



人手不足とは言え、好きな業種、会社に入れるわけではないですもんね。



そうなんですよ。発達障害の方にとって続けるのが困難な環境や職場ばかりから採用オファーがあっても長続きしませんからね。



それに優良企業ほど人は辞めないので、そもそも採用枠自体が少ないこともあります。



発達障害を持つ人が逃げるように転職しなくてもいいよう、さまざまなサポートを受けられる環境が整ったり、周囲の理解が進む社会になればと願っております。



転職回数に限りがあるというお話は、発達障害を持つ人以外にも言えることなので、皆様も参考にしていただければ幸いです。



本日はありがとうございました!



こちらこそありがとうございました!
発達障害のある方にとって、転職を繰り返すことは必ずしも望ましい選択ではありません。
転職を重ねることで、現在の環境よりも状況が悪化してしまう可能性もあります。
また、実質的に転職の回数には限りがあり、いつまでも転職という手段を取り続けられるわけではありません。
そのため、職場での理解を得ることや、カウンセラーや専門家などの外部サポートを活用しながら、成長できる環境を見つけることが理想的です。


本記事に記載されている特徴は、発達障害を持つ全ての個人に当てはまるわけではなく、個人差があることをご留意ください。
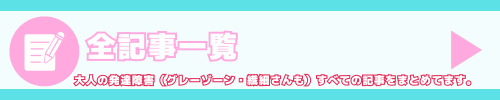
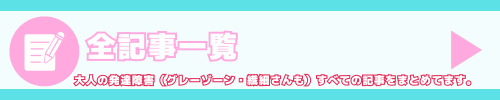


大人の発達障害@暮らし情報館とは



大人の発達障害@暮らし情報館について
大人の発達障害やグレーゾーンの方、またはご家族・職場の方・ご友人・パートナーに向けて、日常生活や仕事、人間関係をより安心して過ごすための工夫やヒントをわかりやすく紹介します。
家族や友人との関わり方、職場での伝え方、暮らしを整える方法など、社会生活全般に役立つ情報をお届けします。
本サイトの内容は、誤解を招きにくい表現に配慮しながら実践に移しやすい形に整理しています。
※本サイトは医療・法律・労務の専門的助言を提供するものではありません。個別の判断が必要な場合は、専門機関へご相談ください。



ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こちらの記事が少しでもお役に立てれば幸いです。