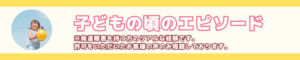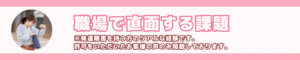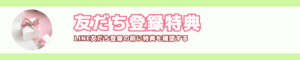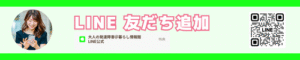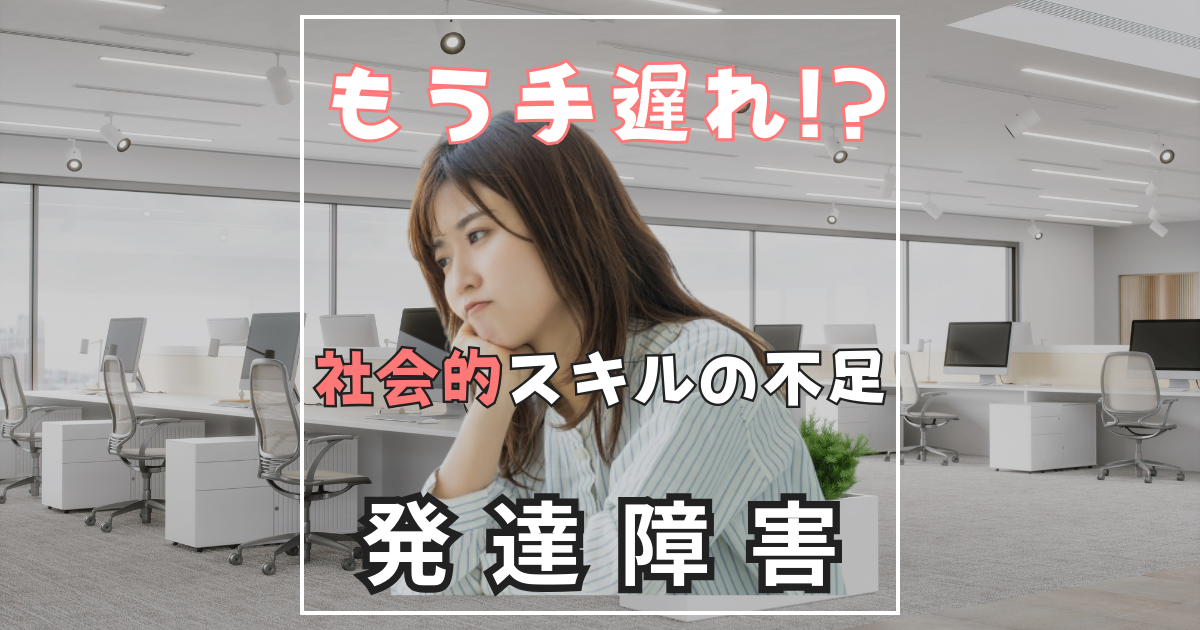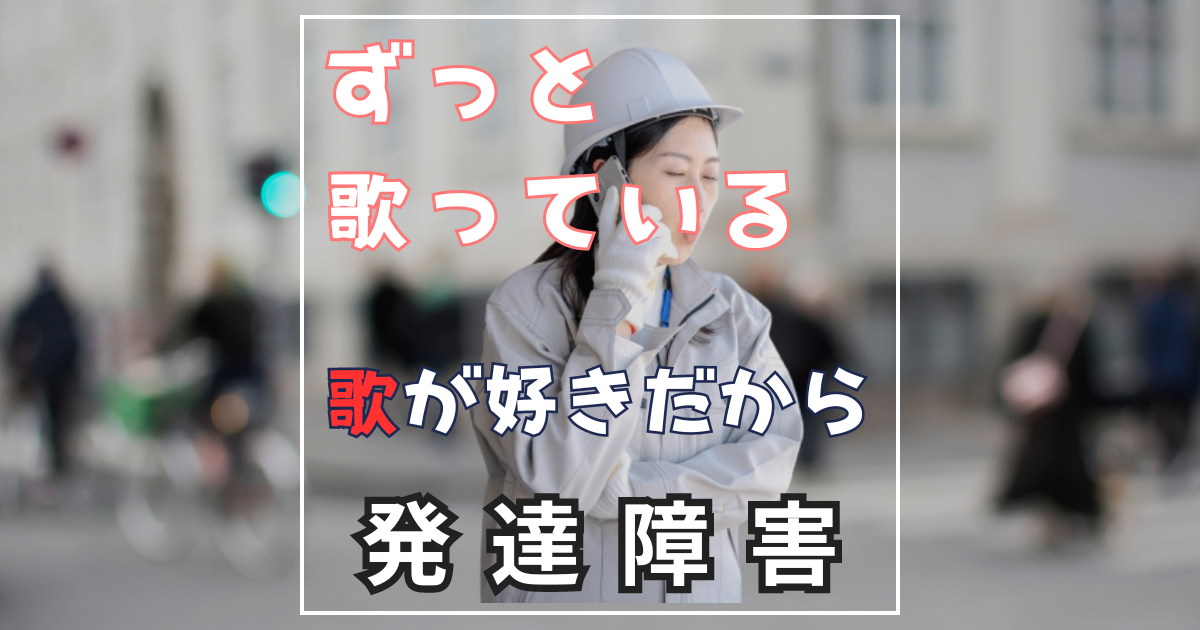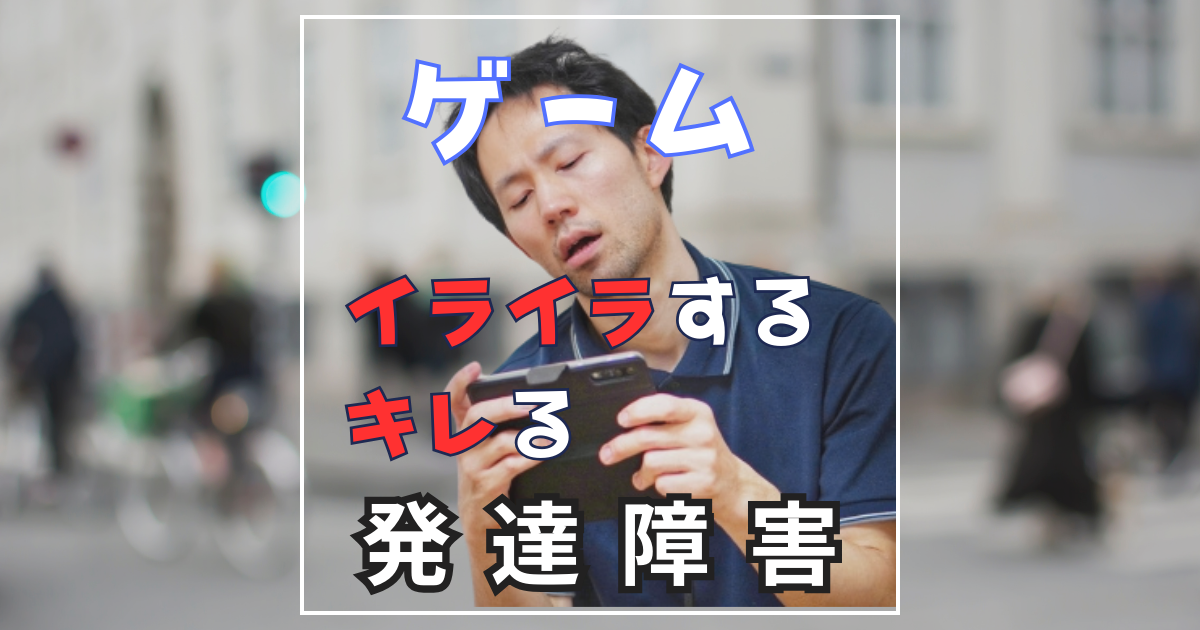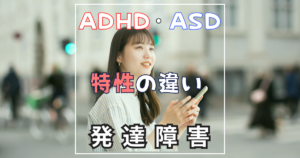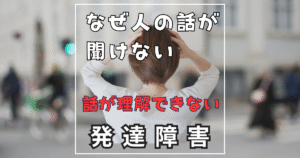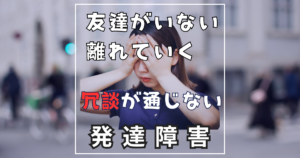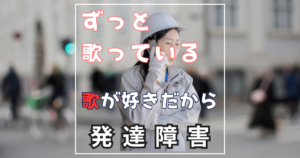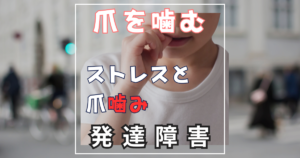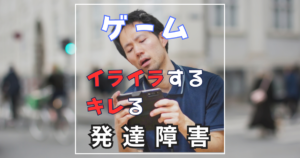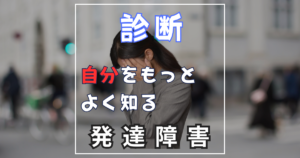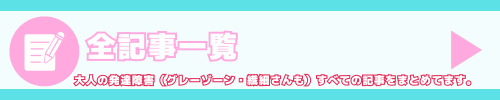
発達障害という言葉を聞くと、多くの人は子どもの頃の問題として捉えるかもしれません。
しかし、発達障害は成長とともに消えるものではなく、成人してからもその影響を感じることがあります。
最近では、社会での経験や生活の変化を通じて大人になってから自分の発達障害に気づく人が増えています。
それでも、診断を受けた時に「今さらどうすればいいのか?」と不安を抱える方も少なくありません。
大人になってから発達障害と向き合うことは、本当に手遅れなのでしょうか?
この記事では、この問いに答えながら、診断の意義や生活改善の可能性について考えていきます。

大人の発達障害 【大人の発達障害は手遅れ?/大人の発達障害 手遅れ】
発達障害は、通常、幼少期から特性があらわれ始め、その症状は大人になっても続きます。
多くは幼少期に発達障害であると気付かれますが、中には個性として見過ごされてしまい、大人になってから発覚するケースもあります。
大人になってから発達障害の診断を受けることについて、多くの誤解が存在します。
たとえば、一部の意見として、大人になってからの発達障害の診断は「無意味」、「もう遅い」、「手遅れ」と思う方もいます。
しかし、これらの認識は間違っています。
大人になってから発達障害であると診断されても、しっかり向き合うことで、個人の生活の質を大きく改善できます。
本記事では、「手遅れ」と感じる理由や、その誤解を解きながら、発達障害を抱える方がどのように生活改善の一歩を踏み出せるのかを考えていきます。

個人の生活の質とは、職場の人間関係や仕事、プライベートなことを含む生活全てのことですね!
大人の発達障害 【大人の発達障害は手遅れと思われてしまう理由】
大人になってからの発達障害の診断を「無意味」、「もう遅い」、「手遅れ」と思ってしまう理由は、いくつかの誤解や偏見に基づいています。
なぜ、誤解や偏見が生じるのか…?
紐解いていきましょう。
発達障害は子どもだけの問題であるという誤解
発達障害をよく知らない人の中には、発達障害の症状は子どもの時期特有のもので、成長と共に改善されていくものであると誤った認識をしている人もいます。
そのため、成人してから診断されると、「なぜ子どもの頃に発見されなかったのか」、「なぜ大人になっても治っていないのか」と疑問を持つことがあります。
これが、大人の発達障害の診断に対して「手遅れ」という誤解を生み出します。
発達障害に対する知識不足
発達障害についての知識が不足しているため、多くの人が大人の発達障害の影響やその管理方法を理解していません。
診断されたとしても、どのように対処すればよいか、どのような支援が利用できるのかがわからないため、診断の意義を見出せないことがあります。
発達障害への差別と偏見
大人として「普通」に機能することが期待される世の中において、診断を受けることで「普通ではない」とレッテルを貼られることを恐れる人もいます。
発達障害に対する社会的な差別や偏見が、大人の発達障害への診断を困難にしています。
治療や支援への誤解
大人の発達障害に対して、治療や支援が有効であるという情報が一般にはあまり知られていません。
そのため、診断することの利点や改善の可能性を理解できず、「今さら何を変えられるのか」と感じてしまうことがあります。
これは本人のみならず、親も同じような気持ちを抱くこともあり、診断に対してネガティブな気持ちになってしまいます。



発達障害は通常、子どもの頃に症状が現れますが、すべてのケースで早期に発見されるわけではありません。大人になって初めて診断されるケースも少なくありません。
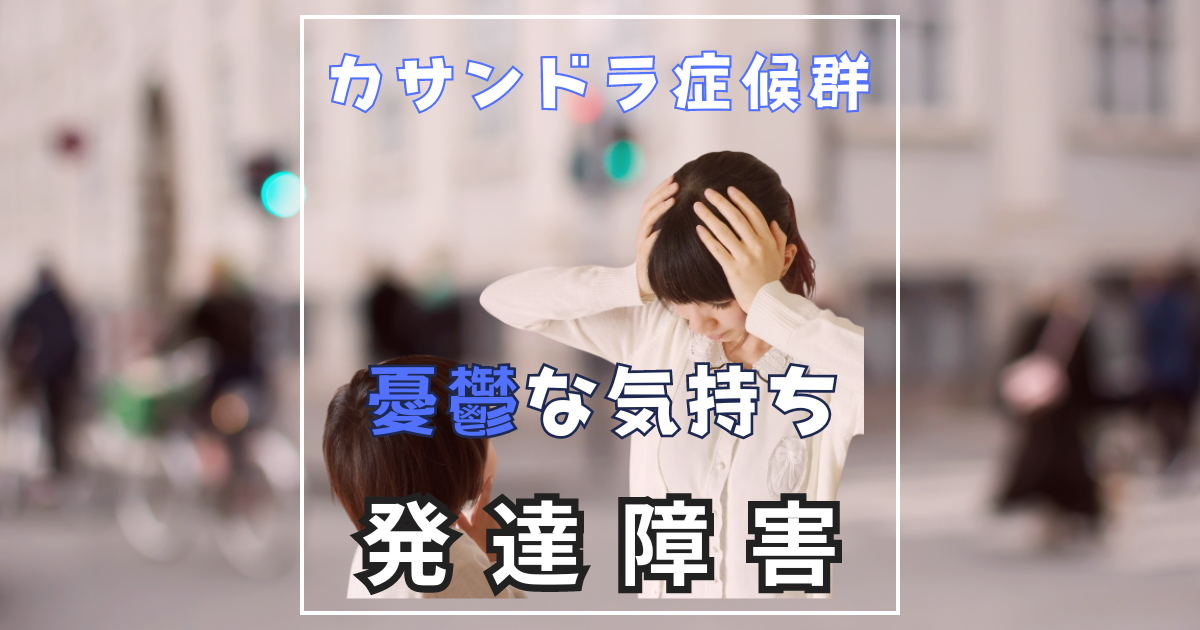
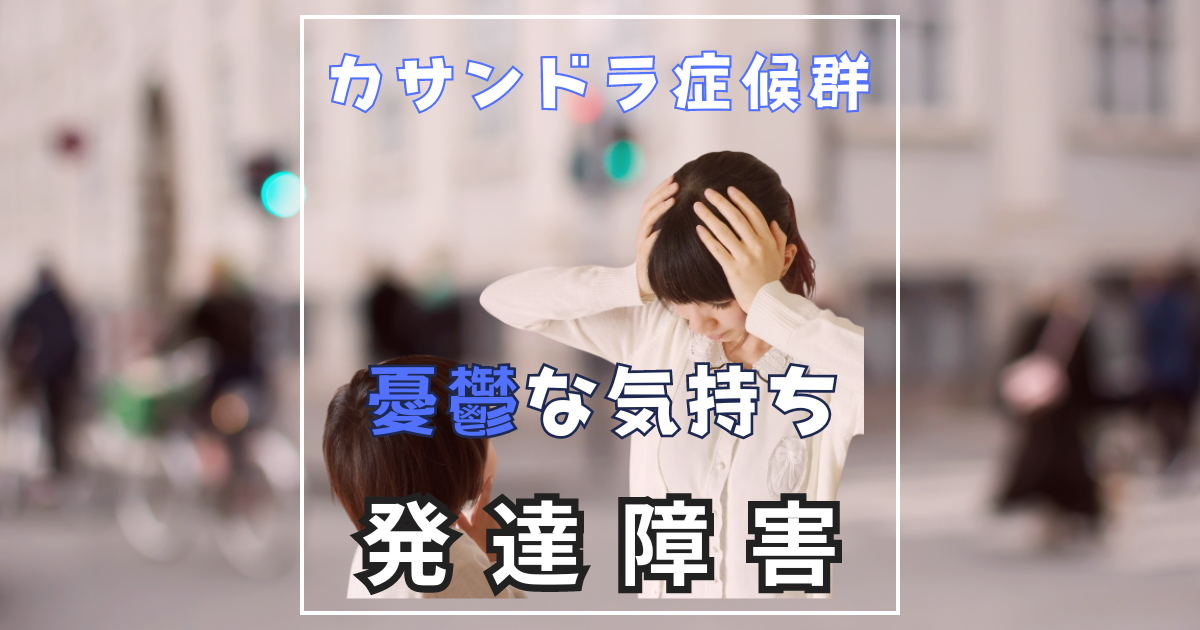
大人の発達障害 なぜ、大人になってはじめて診断されるケースもあるのか
大人になってから、初めて発達障害の診断を受ける理由をみていきましょう。
症状の見落としや誤解
発達障害の症状は、子どもの時期の行動として誤解されがちです。
たとえば、活発な子どもが注意欠如ではなく、「元気がいい」と評価されることがあります。
また、学習障害を持つ子どもが「怠けている」とか「努力が足りない」と誤解されることもあります。
発達障害の症状が軽度である場合
症状が軽度な場合、学校や家庭内では問題が顕著になりにくいです。
そして、症状が軽度であるために簡単な自己管理の方法を見つけやすく、大人になるまで診断されないことがよくあります。
※子どもの社会、学生という複雑なことが要求されない場面においては、簡単な自己管理や学校や家庭内での管理により、発達障害による影響が少ないケースがあります。
社会的な変化による影響の顕在化
子どもの頃は家族や教師のサポートがあり、生活環境も安定しているため、問題が表面化しにくいです。
しかし、大人になると、職場や大学といった新たな環境に適応する中で、自己管理の難しさや社会的スキルの不足が目立つようになり、その結果として「発達障害」と診断されるケースが増えます。
自己認識の向上
大人になると、自分の行動や日々の問題に対して「これって発達障害の特徴なのでは?」と気付くことがあります。
特に、同じように発達障害を持つ人々との会話や、ネットや書籍から得た情報を通じて、自分の特性に気付くきっかけが生まれることが多いです。
診断と認識の進展
医学的な診断基準の変化や発達障害の認知度の高まりも、成人期の診断が増える一因です。
近年、アメリカの精神医学会の定める診断基準(DSM-5)の改訂によって発達障害の診断がしやすくなりました。
また、近年、発達障害に対する認知度が高まり受診する人が増えたことで、大人になって発達障害の診断を受けるケースも多く見られます。



関連記事「子どもの時はまさか発達障害とは思いもしなかった」こちらもご確認ください。


大人の発達障害 【大人の発達障害は手遅れではない】
大人になってから発達障害がわかることは、決して手遅れではありません。
自分がどういう人か、何に弱くて何が得意かをちゃんと知ることが、生活を良くする最初の一歩です。
自分のことを理解していると、自分にぴったりのサポートや環境を整えやすくなり、毎日がずっと楽になり、日常生活が格段に改善されます。
また、サポートやカウンセリングから、どういう行動や対処法が適切であるかアドバイスを受けることもできます。
具体的な行動に対するアドバイス例
- 計算が苦手な場合:電卓を使うことで、計算ミスや負担を減らし、効率よく作業が進められます。
- 時間管理が苦手な場合:目覚まし時計やスマートフォンのリマインダー機能を活用し、スケジュール管理をサポートすることで、忘れがちな予定や遅刻を防げます。
- 物事の優先順位をつけるのが苦手な場合:重要な仕事を書き出し、視覚化することで、何に集中すべきかが明確になり、効率的に作業を進められます。
- 忘れ物が多い場合:メモやチェックリストを活用し、持ち物や日々のやることを確認する習慣をつけることで、忘れ物や抜け漏れを防ぎます。
- 睡眠リズムが乱れやすい場合:就寝時間を固定し、夜間のリラックスルーティンを作ることで、より安定した睡眠を確保し、朝の準備がスムーズになります。
発達障害を持つ方は、他の人にはない独自の才能を持っている場合が多く、その強みを活かすことで大きな成果を上げることができます。
たとえば、細部に目を向ける力や独自の視点が職場で役立つことがあり、周囲の期待以上の結果を出すこともあります。
大切なのは、困難を一人で抱え込まず、ツールや環境をうまく利用しながら、自分らしい働き方や生活スタイルを見つけることです。
これにより、ストレスを減らし、日常生活をより楽しく、充実したものにすることができるのです。



大人になってから発達障害と診断されることは、手遅れではありません。
むしろ、判明した時が自分らしく歩む第一歩となります。
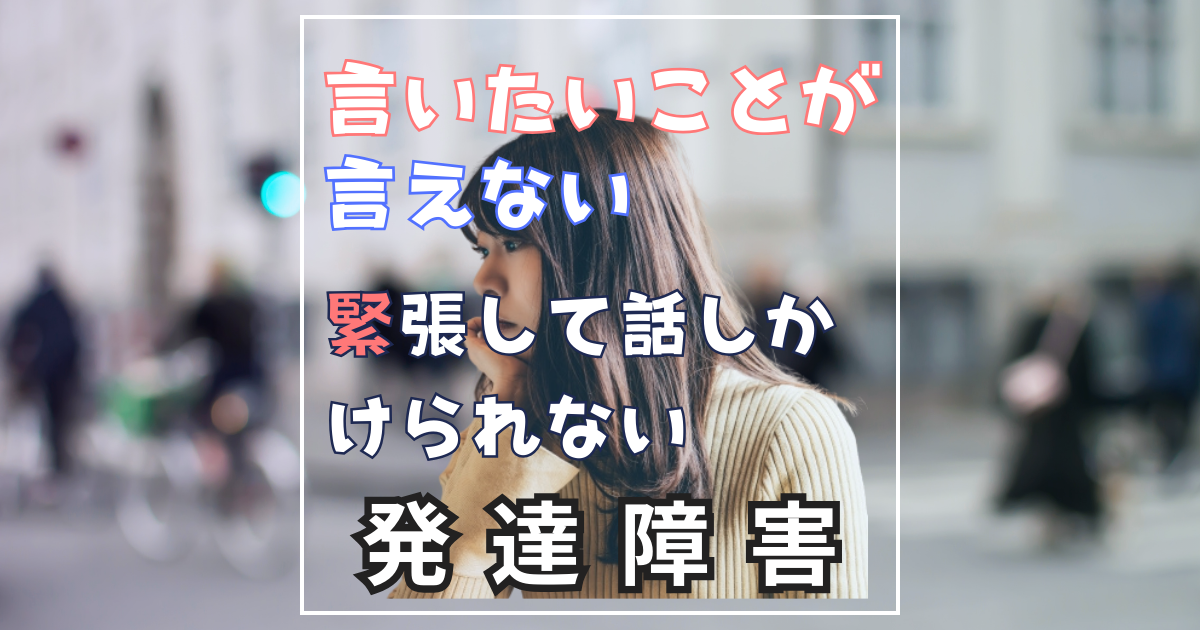
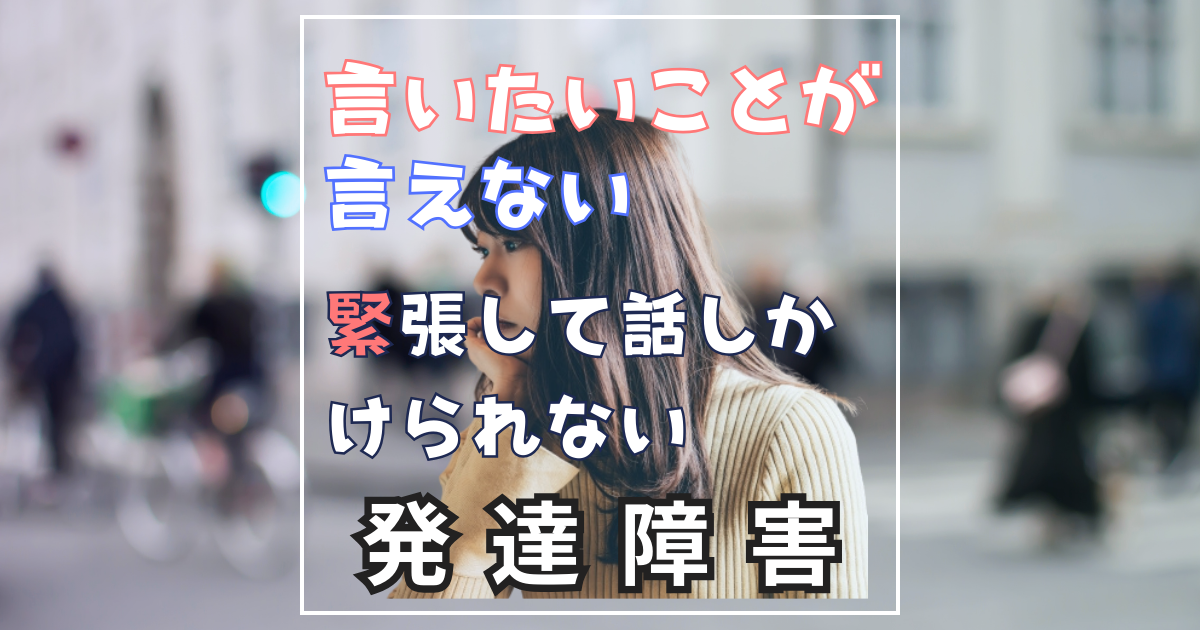
本記事に記載されている特徴は、発達障害を持つ全ての個人に当てはまるわけではなく、個人差があることをご留意ください。
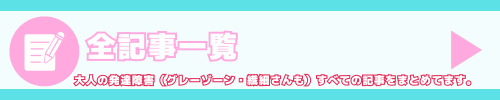
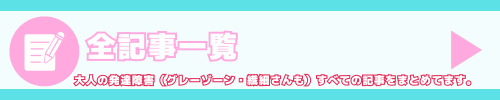


大人の発達障害@暮らし情報館とは



大人の発達障害@暮らし情報館について
大人の発達障害やグレーゾーンの方、またはご家族・職場の方・ご友人・パートナーに向けて、日常生活や仕事、人間関係をより安心して過ごすための工夫やヒントをわかりやすく紹介します。
家族や友人との関わり方、職場での伝え方、暮らしを整える方法など、社会生活全般に役立つ情報をお届けします。
本サイトの内容は、誤解を招きにくい表現に配慮しながら実践に移しやすい形に整理しています。
※本サイトは医療・法律・労務の専門的助言を提供するものではありません。個別の判断が必要な場合は、専門機関へご相談ください。



ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こちらの記事が少しでもお役に立てれば幸いです。