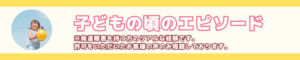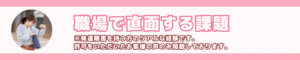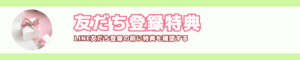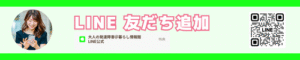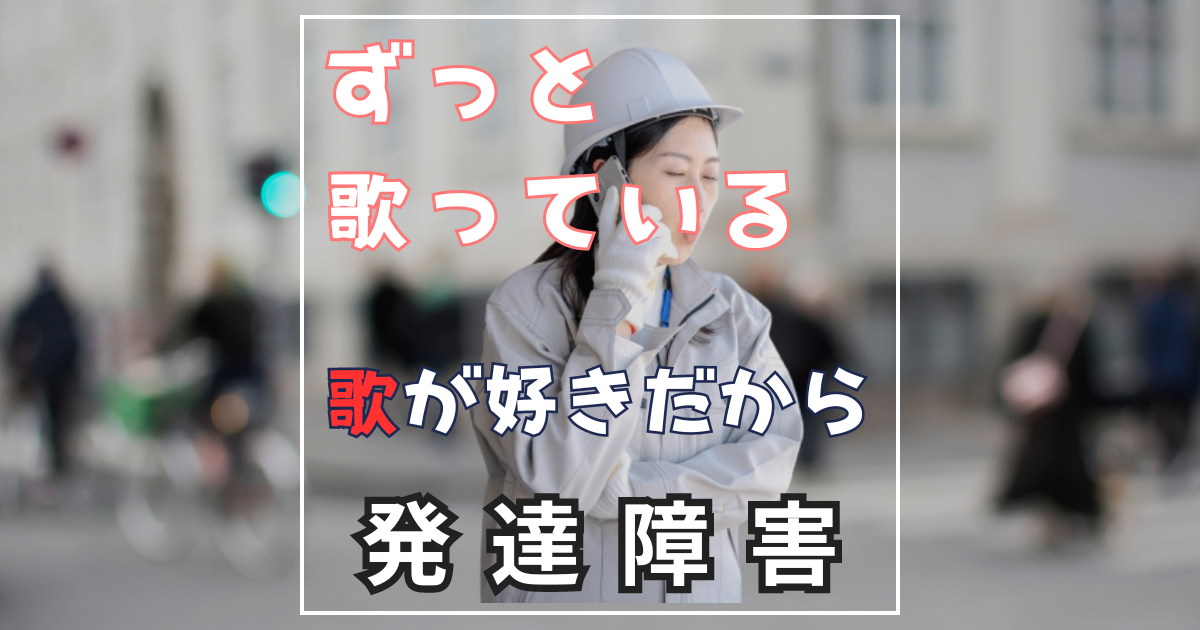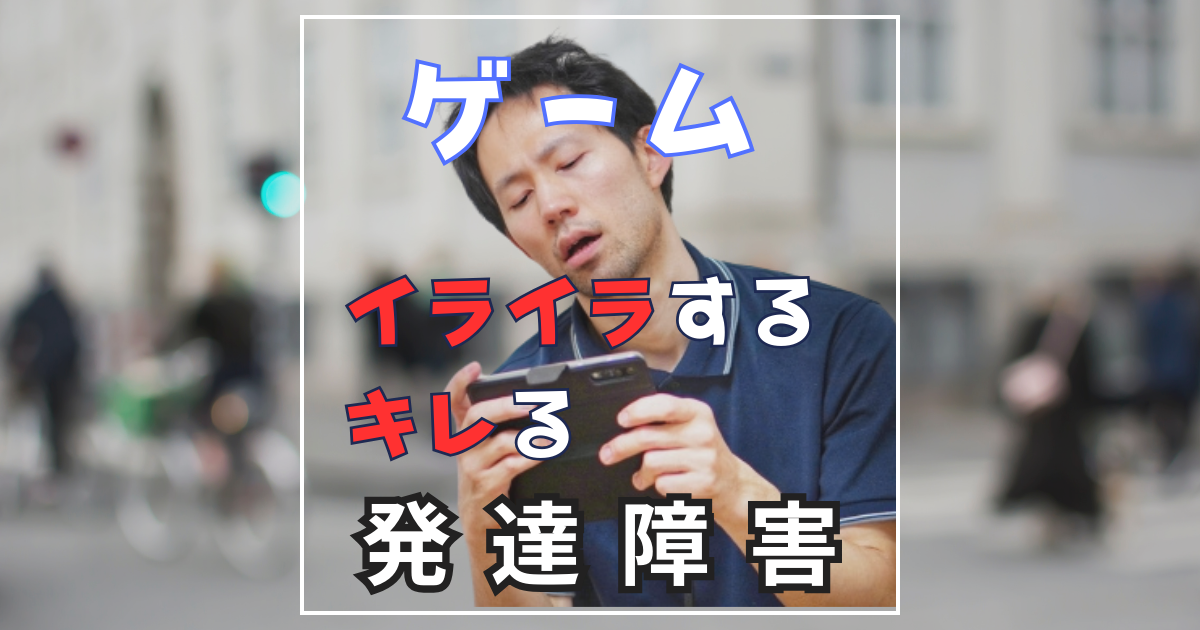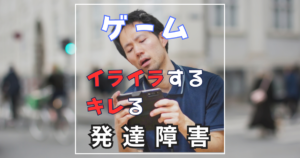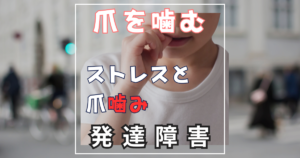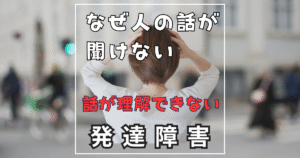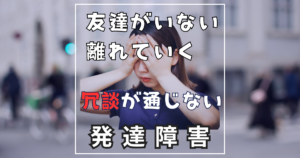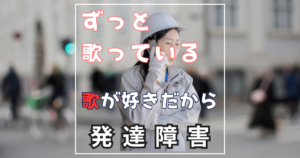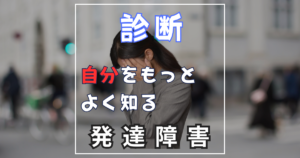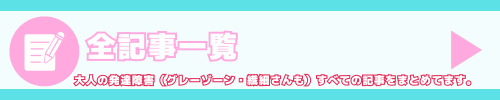
発達障害と「0か100」の極端な考え方 — 白黒思考の影響とは?
私たちは日常生活の中で、時折「物事をどう考えるべきか」という悩みに直面することがあります。
特に、発達障害を持つ人々にとって、物事を柔軟に捉えることが難しい場合があります。
中でも「0か100」という極端な考え方、いわゆる白黒思考が目立つことが少なくありません。
このような思考パターンは、仕事や人間関係に大きな影響を及ぼし、時にはストレスや誤解の原因となることもあります。
では、なぜこのような極端な考え方が生じるのか、そしてどのように対応すればよいのでしょうか。
本記事では、発達障害と「0か100」の極端な考え方について詳しく解説し、その影響や解決策を探っていきます。

「0か100」という極端な考え方、いわゆる白黒思考は、発達障害を持つ人々に見られる特徴の一つです。このような思考パターンがどのように生活に影響を与えるのでしょうか?
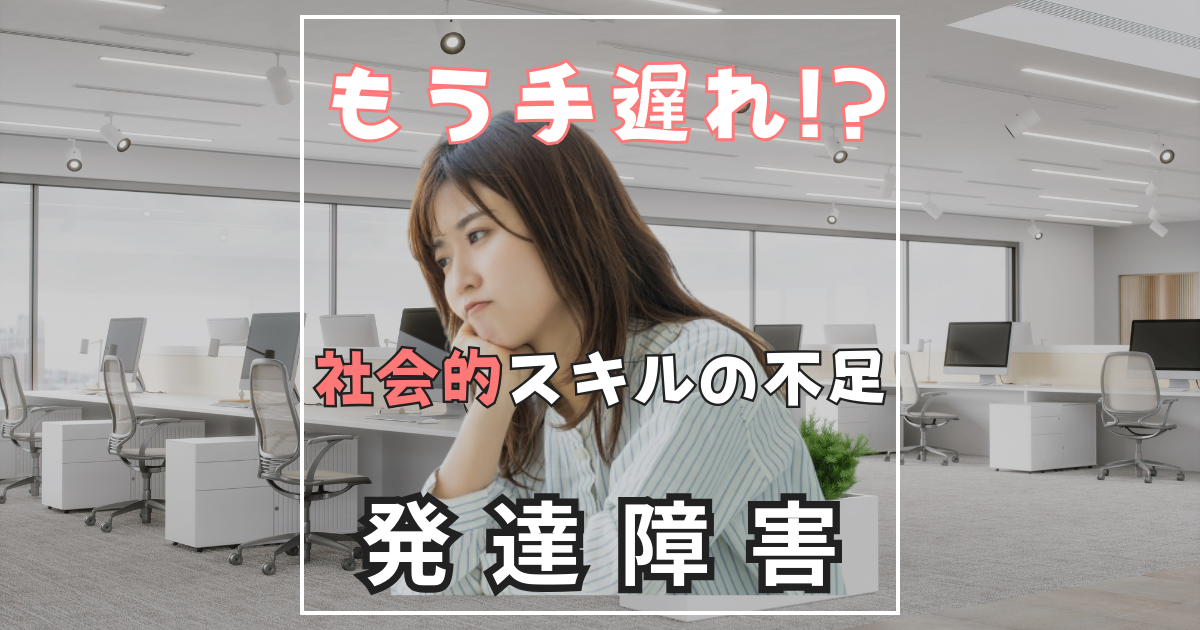
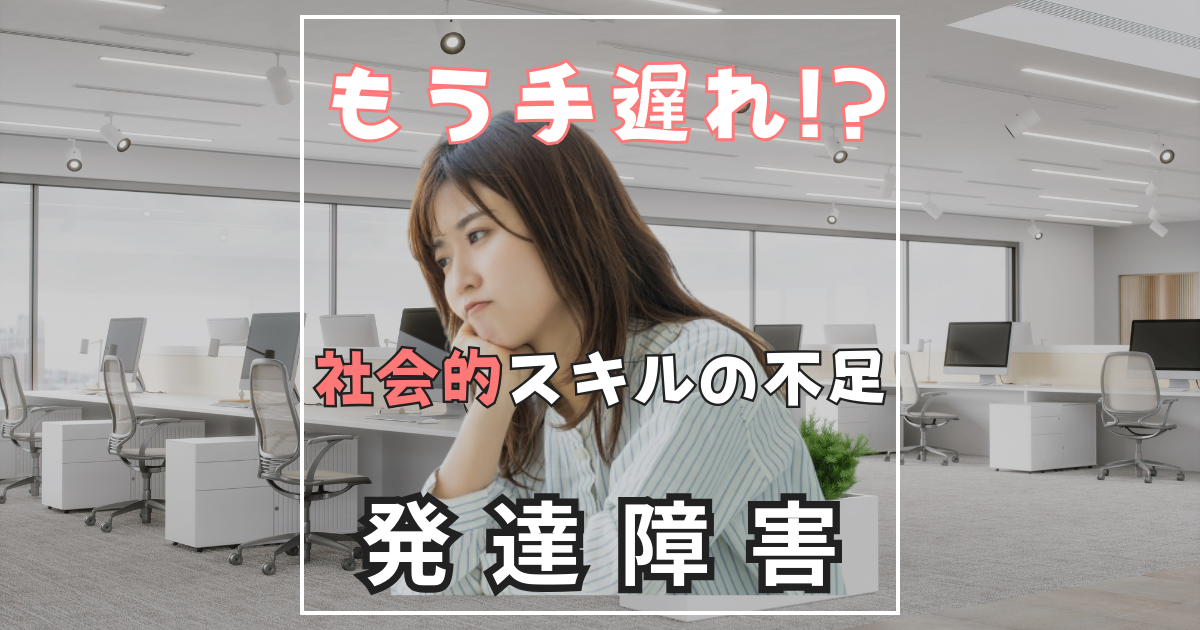


白黒思考とは何か?
白黒思考は、簡単に言うと”物事を『ゼロか全部か』のように、極端に考えてしまうクセのこと”です。
物事を「良いか悪いか」・「成功か失敗か」といった形で判断し、中間的な視点や柔軟な解釈が難しい状態を指します。
発達障害を持つ人は、こうした思考に陥りやすい傾向があり、特にアスペルガー症候群(現在の自閉スペクトラム症の一部)やADHDの方に見られます。
たとえば、「少しの失敗=すべてが失敗」・「1つのミス=自分は無能だ」といった極端な結論に至りやすく、日常生活や人間関係において大きなストレスや誤解を生む原因となります。
白黒思考の例
仕事でのケース
プロジェクト
プロジェクトの一部が計画通りに進まず失敗した時、全体的な成果があったにもかかわらず、
「このプロジェクトは完全に失敗した」と捉え、努力が無駄だったと感じてしまう。
上司の評価
上司から少し改善点を指摘された時、「自分は全く評価されていない」「上司は自分のことを嫌っている」と極端に解釈してしまい、自信を失う。
日常生活でのケース
家事や子育て
掃除が少し不完全だった場合、「私は家事が全くできない」と感じ、他の家事がしっかりできていても自分を過度に責めてしまう。
対人関係
友人が約束を一度忘れただけで、「この人は自分を大切に思っていない」「もう友達を続ける意味がない」と決めつけ、友人関係を断ち切ろうとする。
健康管理
健康のためにダイエットをしているが、1日だけ食べ過ぎた場合、「ダイエットはもう意味がない」「これ以上やっても無駄だ」と全体を否定してしまう。
恋愛でのケース
パートナーの小さなミス
パートナーが約束の時間に少し遅れただけで、「この人は私のことを大切にしていない」「もう信頼できない」と極端に感じ、関係全体を否定してしまう。
意見の不一致
小さな意見の違いがあった場合、「私たちは全く合わない」「このままでは別れるしかない」と、1つの意見の違いが関係全体に悪影響を与えていると判断してしまう。
自己評価
一度振られた経験があると、「自分は恋愛に向いていない」「誰からも愛されない」と感じ、恋愛そのものを避けるようになる。
パートナーの感情表現
パートナーが忙しくて一時的に連絡が少なくなると、「もう自分に興味がない」「愛されていない」と感じ、関係が終わったと思い込む。
自分の失敗に対する捉え方
自分がちょっとした過ちを犯した時に、「こんなことをしてしまう自分は最悪だ」「もうパートナーに見放されるに違いない」と、自分を過度に責めてしまう。


なぜ発達障害を持つ人は極端な考え方をしやすいのか?
発達障害を持つ人が白黒思考に陥りやすい主な理由は、脳の情報処理の違いや感情の調整機能に起因しています。
より具体的に見ていきましょう。
脳の情報処理
発達障害を持つ人は、細部に集中する傾向があり、全体像を柔軟に捉えるのが難しいことがあります。
そのため、物事を単純化して理解することで、過剰な情報処理を回避しようとします。
この結果、複雑な問題でも「良いか悪いか」「成功か失敗か」という二極に分けて考えることが多くなります。
感情の調整が難しい
発達障害を持つ人は、感情の調整が難しい場合があります。
これにより、失敗や困難に直面した時、感情的に極端な反応を示しやすくなります。
たとえば、少しのミスでも大きな失敗と感じてしまい、自分自身を過度に責めることがあります。
ASDとADHD 白黒思考表
| 項目 | ASD(自閉スペクトラム症) | ADHD(注意欠如・多動症) |
|---|---|---|
| 白黒思考の特徴 | 曖昧さが苦手で、 物事を極端に二分しやすい | 感情的な場面で、 極端な思考に陥りやすい。 |
| 認知の柔軟性 | 柔軟な思考が難しく、規則や一貫性を重視 | 通常は柔軟だが、 集中力不足で極端な判断をしがち |
| 感情の影響 | 感情の影響は少ないが、 失敗を極端に捉えやすい。 | 感情が揺れやすく、判断が感情に左右されやすい。 |
| 人間関係への影響 | 他者を「信頼できるか/できないか」と 二極化しやすい。 | 瞬間的な感情で判断し、誤解を招きやすい。 |
| 失敗への反応 | 小さな失敗を大きく捉え、自己評価が下がりやすい。 | 失敗に感情的に反応し、一時的に自信を喪失。 |
ストレスの影響 | ストレスが白黒思考を強化する。 | ストレスで感情の調整が難しくなり、極端な判断をする。 |
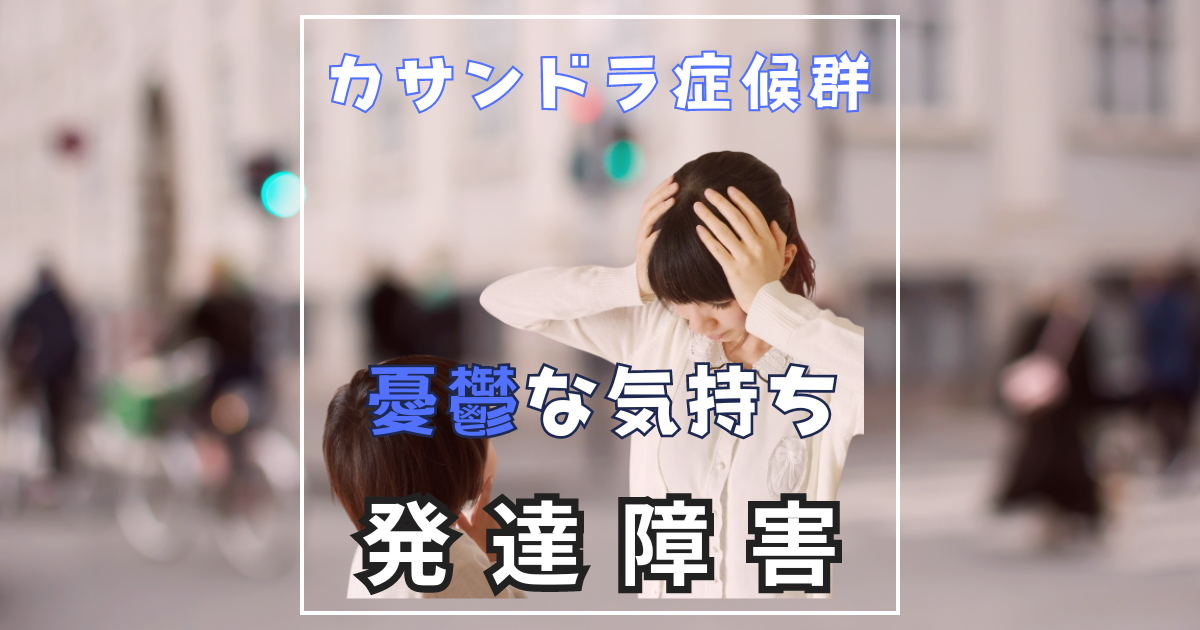
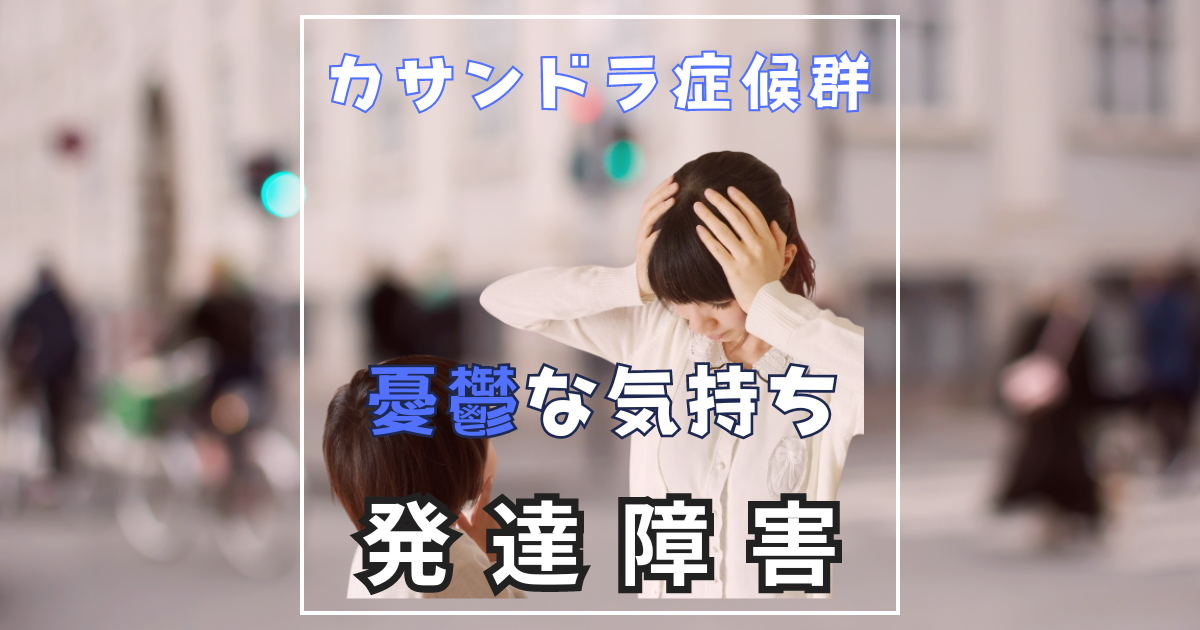
白黒思考の問題点とその影響
白黒思考は、物事を「正しいか間違っているか」のように二極化して捉えやすく、柔軟な考え方が難しくなる傾向があります。
このため、次のような場面で特に強い影響を与えます。
人間関係
白黒思考は、他者との関係において大きな問題を引き起こすことがあります。
たとえば、他人の小さなミスを許容できず、「この人は信用できない」と一方的に結論づけてしまうことが考えられます。
また、自分自身にも厳しく、「完璧にできないならやらない方がいい」といった思考に陥りがちです。
自己評価の低下
一度の失敗を全体の失敗と捉える白黒思考は、自尊心の低下に繋がることがあります。
たとえば、「今日、1つの仕事をうまくできなかった=自分は無能だ」という極端な考え方によって、自己否定が強まり、自己評価がどんどん低くなってしまいます。
ストレスの増加
中間的な評価や柔軟な考え方ができないため、物事に対するストレスが過度に増加することがあります。
何かを完璧にできなければ、それを大きな問題と捉え、過度なプレッシャーを感じてしまいます。
白黒思考の改善方法
白黒思考から脱却するためには、どういったステップを踏むことが重要でしょうか?
物事を二極的に捉える癖を改善するためには、まずその思考パターンを自覚し、少しずつ柔軟な視点を取り入れる必要があります。
以下では、そのために役立つ具体的な方法をいくつか紹介し、実践的なアドバイスをお伝えします。
認知の修正を行う
認知行動療法(CBT)などを活用して、物事を多角的に見る訓練を行います。
「全てがダメだ」と考えるのではなく、「今日は一部うまくいかなかったが、全体的には問題ない」というように、中間的な見方を学びます。
このような認知の修正が、極端な思考を和らげる第一歩です。
感情のコントロールを学ぶ
感情の調整が難しい場合、マインドフルネスやリラクゼーション技術を活用して、ストレスや不安を軽減することが効果的です。
感情が落ち着くことで、冷静に物事を判断し、極端な結論を避けることができるようになります。
柔軟な思考の訓練
柔軟な考え方を身につけるために、異なる視点を持つことを意識的に練習します。
たとえば、「すべてが完璧でなければいけない」と考えるのではなく、「少しの失敗は学びの機会」と捉えることで、物事に対するプレッシャーが軽減されます。
発達障害を持つ方にとって、白黒思考は生活に大きな影響を与えることがあります。
しかし、認知の修正や感情のコントロールを学ぶことで、柔軟な考え方を身につけ、生活の質を向上させることが可能です。
まずは、自分自身の思考パターンに気づき、少しずつそれを改善していくことが重要です。
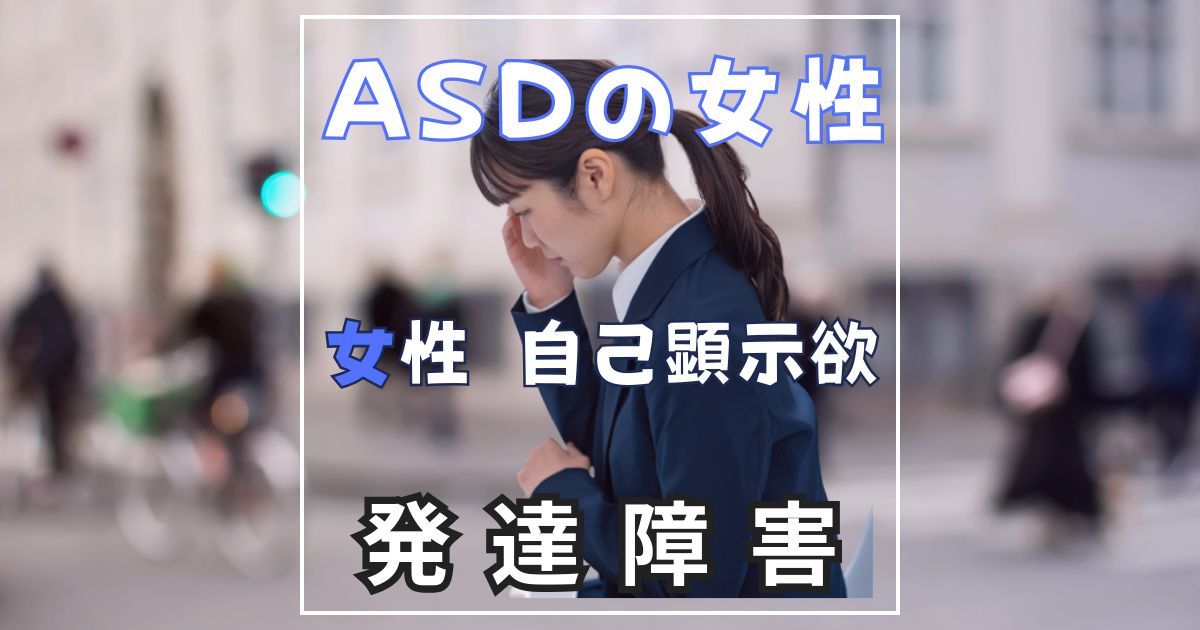
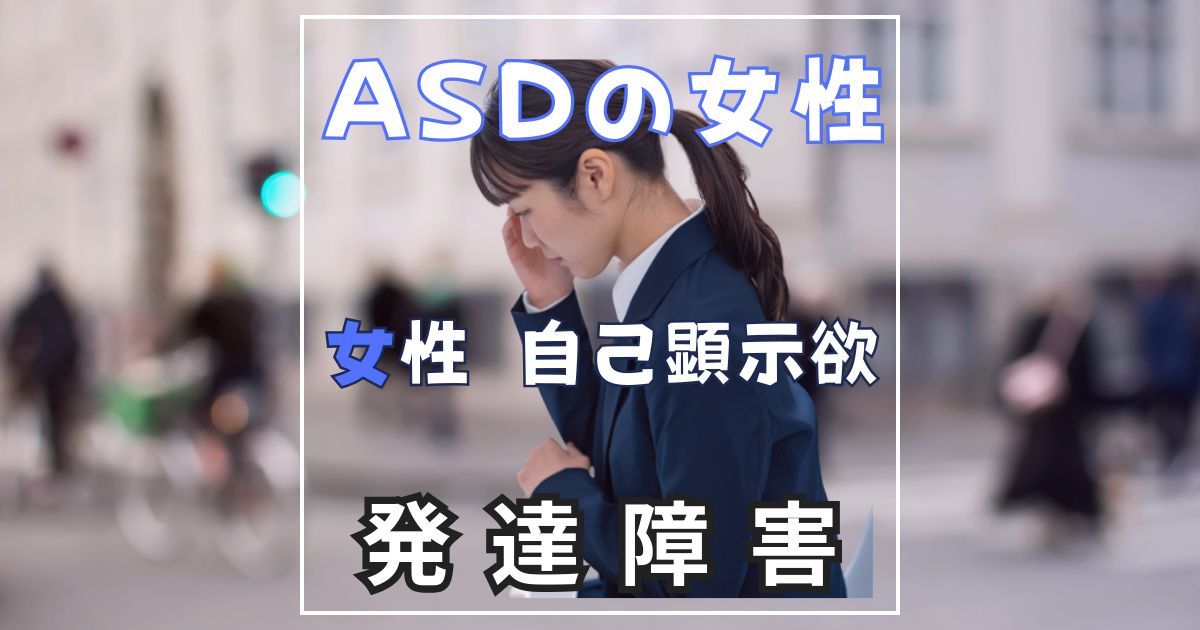
本記事に記載されている特徴は、発達障害を持つ全ての個人に当てはまるわけではなく、個人差があることをご留意ください。
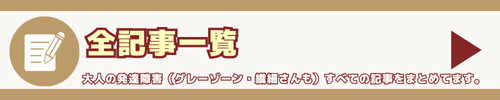
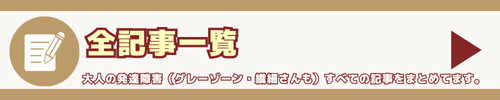


大人の発達障害@暮らし情報館とは



大人の発達障害@暮らし情報館について
大人の発達障害やグレーゾーンの方、またはご家族・職場の方・ご友人・パートナーに向けて、日常生活や仕事、人間関係をより安心して過ごすための工夫やヒントをわかりやすく紹介します。
家族や友人との関わり方、職場での伝え方、暮らしを整える方法など、社会生活全般に役立つ情報をお届けします。
本サイトの内容は、誤解を招きにくい表現に配慮しながら実践に移しやすい形に整理しています。
※本サイトは医療・法律・労務の専門的助言を提供するものではありません。個別の判断が必要な場合は、専門機関へご相談ください。



ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こちらの記事が少しでもお役に立てれば幸いです。