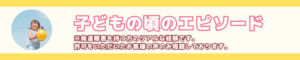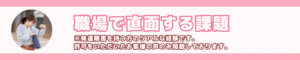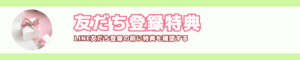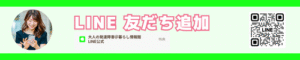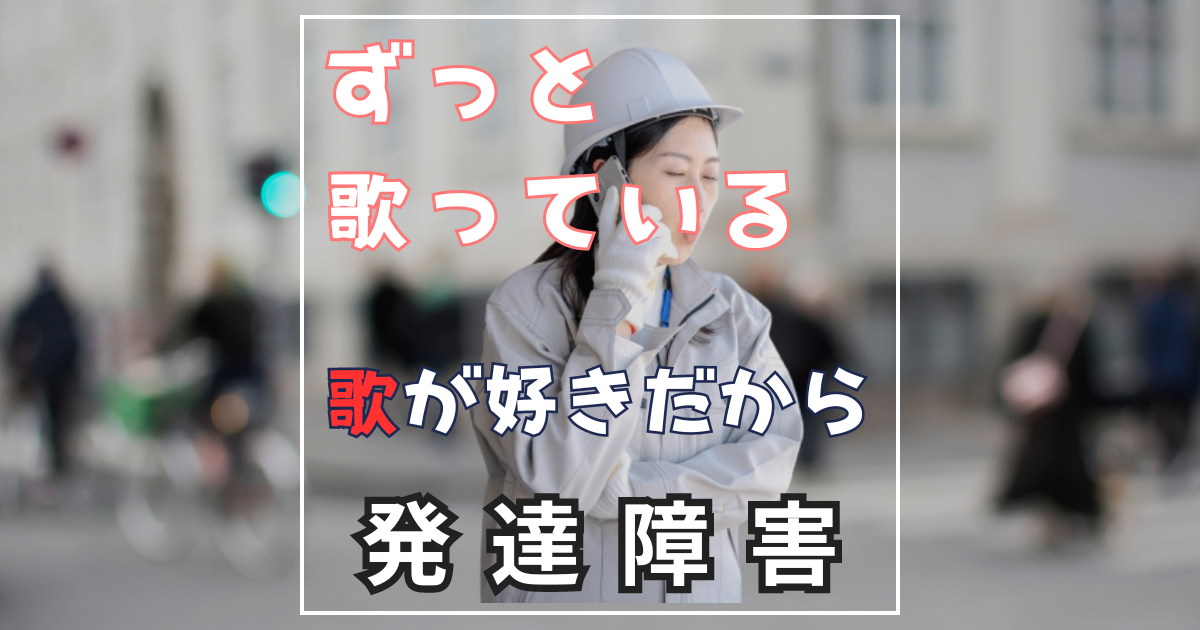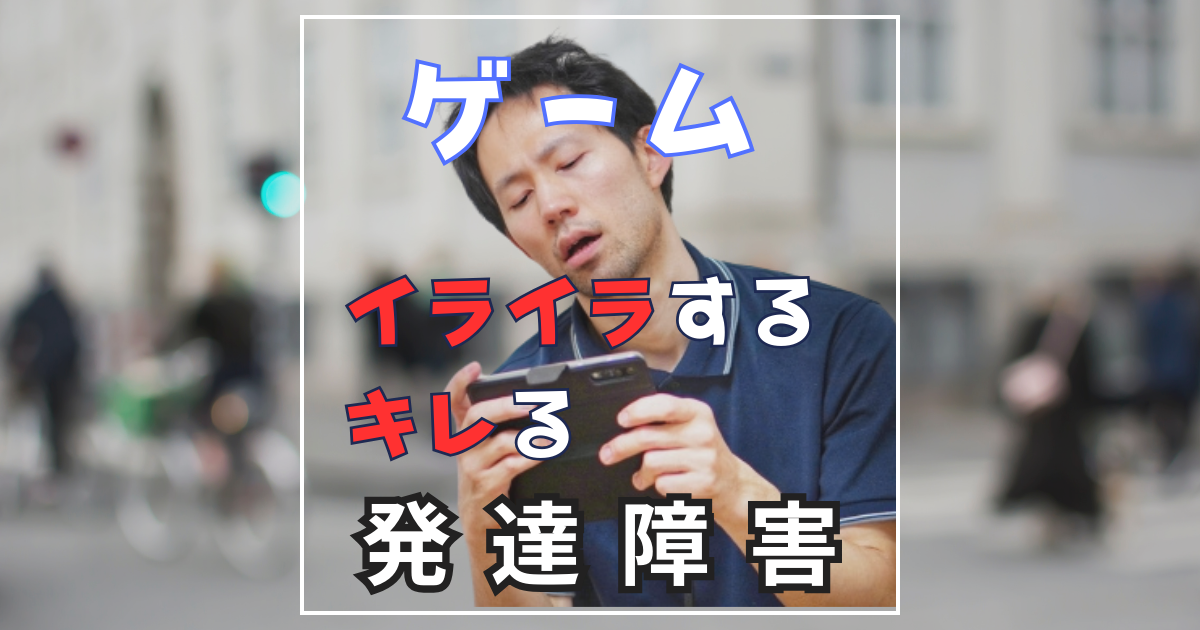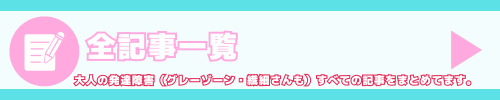
発達障害を持つ大人たちが直面する課題を実体験から考えましょう
発達障害を持つ方々が子ども時代に経験した悩みや課題は、大人になった今でも生活に影響を与えていることが少なくありません。
今回のアンケートでは、発達障害を持つ大人が幼少期に感じた困難や孤立感、周囲との違和感についてのリアルなエピソードを集め、分析しました。
これらの体験を通じて、発達障害の特性を理解し、子ども時代の支援のあり方やその後の成長への影響を深く掘り下げていきます。
記事を読むことで、ご自身やご家族、支援者の方が、発達障害の子どもに対する理解とサポートの手がかりを得る一助となれば幸いです。
どうぞ今後の参考にしてください。
発達障害の特性が浮き彫りになる|子ども時代の本音と悩み
moriさんの子ども時代の体験談
★お名前を教えてください(イニシャル・ニックネーム など可能です)

「mori」です。
★年齢を教えてください



28歳です。
★性別を教えてください



女性です。
★あなたが自覚している発達障害の特性は?



ASD(自閉スペクトラム症)です。
※掲載内容は原文そのままとなっており、誤字や脱字が含まれる場合がございます。ご了承ください。
子どもの頃、注意力が続かないと感じたことは、どのくらいの頻度でありましたか?
選択式 ※青が回答
・毎日のようにあった
・週に何度かあった
・あまりなかった
・ほとんどなかった
他の子どもとの協調性が難しかった場面がありましたか?
選択式 ※青が回答
・いつも感じていた
・時々感じていた
・あまり感じなかった
・まったく感じなかった
子どもの頃、集団活動で困難を感じたことがありましたか?
選択式 ※青が回答
・よくあった
・時々あった
・あまりなかった
・まったくなかった
他の子どもたちと違う行動をとってしまうことで、周りから浮いたように感じたことはありますか?
選択式 ※青が回答
・よくあった
・時々あった
・あまりなかった
・まったくなかった
学校や家で人と目を合わせることが難しかったですか?
選択式 ※青が回答
・とても難しかった
・少し難しかった
・あまり難しくなかった
・まったく難しくなかった
他の子どもに比べて自己主張が苦手だと感じたことはありましたか?
選択式 ※青が回答
・かなり感じた
・少し感じた
・あまり感じなかった
・まったく感じなかった
学校や家庭でのルールや指示が理解しづらいと感じた経験はありますか?
選択 式 ※青が回答
・よくあった
・時々あった
・あまりなかった
・まったくなかった
子どもの頃、特定の行動やこだわりが原因で、周囲とトラブルになったことはありますか?
選択式 ※青が回答
・何度もあった
・時々あった
・あまりなかった
・まったくなかった
子どもの頃、体育の時間や遊びで、他の子たちに比べて不安を感じた経験はありますか?
選択式 ※青が回答
・はい
・いいえ
子どもの頃、失敗を恐れる気持ちが強く、挑戦することが苦手だったと感じることはありましたか?
選択式 ※青が回答
・とても苦手だった
・すこし苦手だった
・あまり苦手ではなかった
・まったく苦手ではなかった
他の子どもと比べて感情がコントロールしにくいと感じたことはありましたか?
選択式 ※青が回答
・かなり感じた
・少し感じた
・あまり感じなかった
・まったく感じなかった
子どもの頃、大きな不安やストレスを抱えやすかったと感じますか?
選択式 ※青が回答
・非常に抱えやすかった
・少し抱えていた
・あまり抱えなかった
・まったく抱えなかった
学校や家庭での指導や指示が理解できなかったとき、どのような気持ちでしたか?
私は先生の指示がわからなくても、みんなは理解できている…それがなぜなのかがわからず、不安でなかなか行動に移せませんでした。
周りの子たちを見て、「つまりこういうことか?」と無理やり納得させて行動に移すことが多かったです。結果として、周囲に合わせた行動を取っているので、間違えた行動を取ったということはないのですが、どうしてみんなはスムーズに動けるのか?なぜ私はすぐに理解して動き出すことができないのか?と悲しく思うことは多かったです。
家庭では、何度か聞き返すことができるので、聞き返してしまうことが多く、親がその都度、付き合って、私がわかりやすいように違う表現で指示をしてくれて、不安感はなく行動できますが、それでも何度も聞き返し確認しなければ行けないことは双方にとって負担だったと思います。
友人や周囲との人間関係で感じた具体的なエピソードがあれば教えてください
人との距離感を計ることが苦手で、自分が好ましく思った相手とはすぐに深い距離感で付き合いたくなってしまいます。
休み時間に一緒にいたがったり、一緒に遊びたがったり、ずっと話しかけてしまったり…。そのため、うっとうしいと思われることも多かったようで、私が一方的に仲良しだと思っていた相手から「ウザい」と陰口を言われていたようでした。
また、相手の表情を読むことがあまり得意ではなかったため、私は相手も楽しんで付き合ってくれていると思っていたのですが、そうではなかったと知ってすごく悲しかったです。
そういうことがあったためか、友人たちは、グループでの遊びに誘われることが少なくなったり、周りが私にわからない話題で盛り上がったり、と自然と私からそのグループを離れるように工していたように思います。それがすごく悲しく、孤独だと思い、いつかわかり合える友人に会えたら、という思いが強くなりました。
強いこだわりなどによって、他の人とトラブルになったことはありますか?
幼稚園の頃は、絶対にその兎のぬいぐるみで遊びたかったです。
教室に一つしかないぬいぐるみで、いつもなら私しか遊ばず、安心して手に持っていることができました。だけどその日は他の男の子が持って行ってしまい、私のぬいぐるみなのに!と泣き出してしまいました。
先生に、おもちゃはみんなのものだよ、と説明を受けても、いつも持っていたぬいぐるみがないことが不安で、その日はずっと先生から離れずすごしていたことを覚えています。
また、ごっこ遊びをしたとき、私は大抵お母さん役で、それが気に入っていました。ですがその日は別の役割を与えられて、やはり、お母さんがよかったのに!と喧嘩になってしまったことがあります。その時は双方の親が側にいたので、互いに慰め、なだめ、結局ごっこ遊びではない遊びをすることになりました。そういうことが多々あったと記憶しています。
他人から誤解を受けやすかった経験はありますか?
人の好意をどこまで真に受けていいのかわからず、基本的には「お礼に掃除当番変わるよ」「お礼におごるよ」といった言葉は全て冗談だと受け取り、断ってきました。
真面目だね、と言われることが多かったですが、中には嫌味のような言われ方もありました。また、いつも断っていたため、「あなたは甘え方を知らないね」とたしなめられたことがあります。
「本気で感謝している、それを示す手段がご馳走することだ、と言っているのだから素直に甘えないと、それはそれで失礼だよ」と言われてしまったことがあり、以来、なるべくお言葉に甘えるようにしています。
ただ、やはり私なんかにそんなお礼をしてくれるとは思えず、どこかで「あいつ図々しいよ」と陰口を言われるのでは、という不安が拭いきれません。
学習や理解の遅れが原因で困ったことやストレスを感じたことはありますか?
授業について行けないことはなく、むしろ成績は優秀でした。
なのでなぜテストの点数が悪いのか、宿題をやらないのか、つい見下してしまうような考えを持つほどでした。
成績がよかった、ということもあり、学習面では先生に頼りにされていることも多く、分らない子の面倒を見てくれと言われることも多かったです。
ただ、私の場合は伝え方、説明の仕方が下手くそで、教えようにも上手く教えられず、もういい!と言われてしまうことも多く、先生に「まだ終わっていないこの子とを見てあげて」と言われることがプレッシャーになりました。なので、すぐにできても提出をせず、クラスの半分くらいの子ができたところで提出するように周囲を見るようになりました。
授業中や自宅での勉強に集中できなかった経験はありましたか?
作文を書いている際などに、先生が見回りに立ち歩き回るのが苦手でした。書き途中のものを見られることが苦痛で仕方ないのです。
先生が歩いている、近づいてくると思うと、途端に自分がなにを書いているのかわからなくなってしまい、先生が教卓に戻るとやっと安心して続きを書き始められました。
なので、作文などの完成は遅い方で、いつも授業時間ギリギリの提出になっていました。
また、筆箱を鳴らしたり椅子を傾けたりと遊ぶ子がいるとそちらに意識が行ってしまい、そうすると先生の説明を聞くことが難しかったです。板書のない口頭説明に関しては書き漏らしてしまうこともあり、後から隣の席の子に「先生が言っていた内容はこれで合っている?」と確認させてもらうことがありました。
宿題や課題の提出についてのエピソードを教えてください
期限の見通しが甘いことはありました。夏休みなどの長期休みの際は、自分の能力を過信して、一週間以内に終わらせる!というような無茶な計画を立て、頓挫し、結局だらだらと宿題をやり続けることになり、夏休みいっぱいかかってしまう、ということが何度かありました。
また、読書感想文が苦手で、なにを読むかというところ空か決めるのが難しく、こちらも期限ギリギリになることが多かったです。
宿題は、ついページの隅に落書きをしてしまい、そうすることで楽しみながら宿題をやり勧めることができたのですが、それを先生に咎められてしまい、そこからは宿題をする時間が苦痛でした。
ただドリルに向き合って勉強するということが苦手で、リフレッシュする時間と勉強する時間を少しずつ交互に設けてやっていました。
集団活動や運動が苦手だった場合、それがどのような影響を与えたか教えてください
運動が苦手で、体育ではチームの足を引っ張ることが多く、同じように運動の苦手な子を見るとホッとしていました。
ある年、休み時間にはクラスみんなで遊ぼう、というクラスになってしまったことがあります。ドッチボールや大縄跳びをするのです。おかげで休み時間は苦痛で仕方がなく、行きたくもないのにトイレに行くと嘘をつき、わざと遅れて参加して、遅れちゃったからこのゲームは見学しておくね、と逃げる術を見つけていました。
ドッチボールのチームわけでは最後まで残るし(ドラフトで好きな子をメンバーに入れていく方法でした)、大縄鳶はまともに飛べないし、惨めで悔しかったです。
今でも運動は大嫌い、特に、人の眼がアルバでの運動は嫌いなので、ジムにも行けません。
感情が抑えられなかったエピソードがあれば教えてください
自分の意見が通らないときは、どう言語化したらいいのかわからなくなり、いつも泣き出してしまいます。
まともに話すことも出来ず、わーっと泣いてしまうので、周りの子たちに気を遣わせてしまい、申し訳なかったです。また、大人たちも手を焼いているようでした。幼稚園の頃は、幼い物同士仕方がない、という雰囲気でしたが、小学校になると「なんでこんなことで泣くの?」というような空気をよく感じ、泣いてはいけないと思うほど泣けてしまい…という悪循環だったと思います。
家では、感情的になると大声を上げてしまったり、物を投げたりということが多く、ご近所さんたちにどう思われていたのか…。親は、暴れる私を強く抱き締めて制していました。
学校や家庭で「普通」とされることに適応できず、葛藤した経験があれば教えてください
人一倍不安を感じることが強く、そのためになかなか行動に移せなかったり、身体が固まってしまうことが多かったです。でも、周りの子たちはそんなことなく、気にせずになんでもこなしているように見えて、なんで私はできないの?と劣等感を抱いていました。
不安を感じると途端になにもできなくなるので、周りの子たちがいろいろなことに挑戦する中、自分だけなにも変わらずその場に立ち尽くしているようで、置いてけぼりになっている感覚もありました。
また、毎日の登校さえ、今日の授業で当てられたらどうしよう、宿題忘れずに持ったかな、忘れていたらどうしよう、と考え込んでしまい、なかなか家を出られずいつもギリギリの出発でした。
その度に、親が大丈夫だから、と声をかけてくれて、なんとかやっとの思いで登校していました。
他の子どもや大人から指摘されたネガティブな特徴や言葉はありますか?
「空気読めないよね」といわれたことは何度もあります。
過剰にルールを守らなければという意識になったり、またルールを破ったことで怒られるかもしれないという養父や不安が強く、周りの子に対しても、やめなよ、やめた方がいいよ、ということをよく言っていました。そのため、楽しい空気をぶちこわしにする人間だと思われている節があったと思います。
その度に、私としては楽しさよりルールを守ることの方が大事だから…と腑に落ちず、悔しく悲しい思いをしていました。
また、休み時間に一人でいたとき、男の子から「誰も友だちいないじゃん」とからかわれたこともあり、図星だなと感じ、思わず涙ぐんでしまいました。他の女の子が庇ってくれましたが、その子は別に友だちというわけでもなく、本当に友だちいないんだな、と自分でも思い、悲しく苦しかったです。
大人になった今、子どもの頃の自分を振り返ってどのように感じていますか?
大人になった今思うと、子ども時代の自分はそれなりに頑張っていたと思います。
だけど、それが少しズレていたのだな、とも。本音をいえば、周りの大人にもっと分かってもらえたら嬉しかったのですが、それは無理なのだから、もっと自分で自分を甘やかしてあげればよかった、と思います。精一杯やっていたのだから。
ただ、周囲とどう合わせていくか、ということは、大人になった今も課題です。子どもの頃にもっと上手くやれていたら、今ももう少し楽なのかな、と思うと、当時から発達障害の特性に対する理解が、もっとあるとよかったな、と思ってしまいます。適切な対応を受けたかった、と思ってしまいますね。
友人や周囲との関係構築において、「相手との距離感を測ることが苦手」「仲良くしたい相手への過度な接触」といった行動が、本人にとっては親しみの表現であっても、相手には負担と感じられやすい点が浮かび上がります。
また、相手の表情や気持ちを察することが難しいため、一方的に仲の良さを信じていた相手から距離を取られるという体験が、孤立感や疎外感を深める要因になっていたことが考えられます。
次に、ルールや特定の行動へのこだわりに関するエピソードでは、共用のぬいぐるみに対する所有意識や役割の希望に執着する場面が見られます。
このような状況での行動は、本人の「安心感」や「慣れ」に対する強いニーズから発生しており、ASD特有の「変化への不安感」が示唆されます。
また、感情のコントロールと他者からの誤解についても触れられており、特に「感謝の表現を受け取るべきかの判断が難しい」といった社会的な駆け引きに不安や負担を感じていた様子が伺えます。
これは、他人の意図を正確に理解することが難しい特性が影響しており、真摯に対応しようとする一方で、思わぬ誤解を受ける場面が少なくなかったことが見受けられます。
最後に、学校生活や家庭生活における不安や適応への困難も、日常の場面でのストレス源となっていたようです。
登校前の不安や、周囲の理解が得られない中で日々「普通」に適応しようと努力したことが、回答者にとって大きな負担となっていました。大人になってからは、当時のズレや対人関係の難しさに対する気づきが生まれ、より自分を理解し、自分自身を肯定する重要性も感じていることが伺えます。
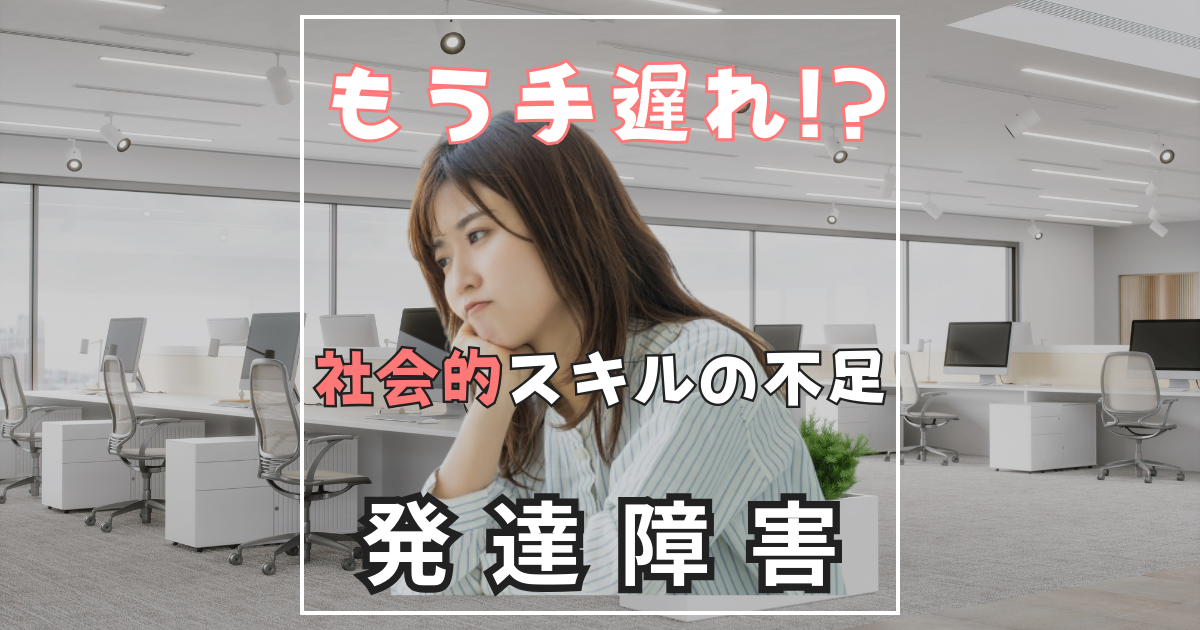
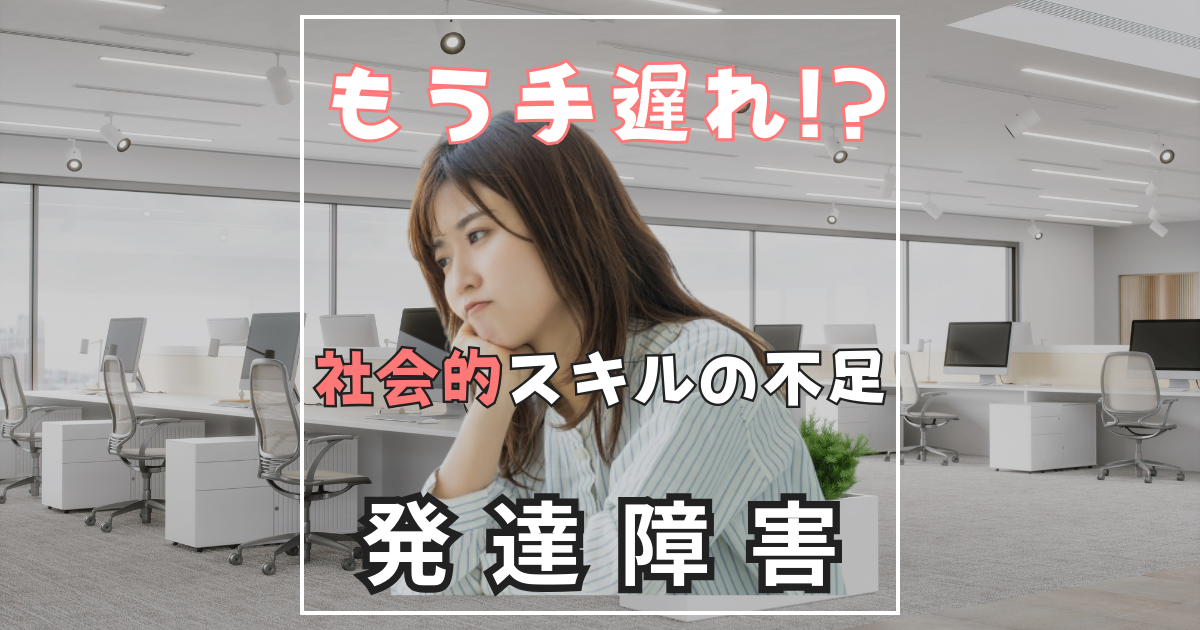
本記事に記載されている特徴は、発達障害を持つ全ての個人に当てはまるわけではなく、個人差があることをご留意ください。
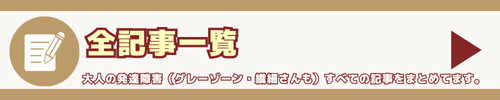
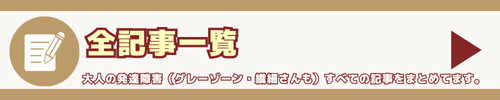
大人の発達障害@暮らし情報館とは



大人の発達障害@暮らし情報館について
大人の発達障害やグレーゾーンの方、またはご家族・職場の方・ご友人・パートナーに向けて、日常生活や仕事、人間関係をより安心して過ごすための工夫やヒントをわかりやすく紹介します。
家族や友人との関わり方、職場での伝え方、暮らしを整える方法など、社会生活全般に役立つ情報をお届けします。
本サイトの内容は、誤解を招きにくい表現に配慮しながら実践に移しやすい形に整理しています。
※本サイトは医療・法律・労務の専門的助言を提供するものではありません。個別の判断が必要な場合は、専門機関へご相談ください。



ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こちらの記事が少しでもお役に立てれば幸いです。